SDGsへの取り組みは、持続可能な社会を
未来の子供たちに残す事業者・大人の
責務の一つと思います。
そして大企業よりも中小企業の方が
一歩踏み出すことはずっと簡単です。
一社一社、一人ひとりの取り組みが
未来によき地球・社会を遺す活動と
経済の両立を果たすことを祈っています。

SDGs Goal.1「貧困をなくそう」で出来ること(国内編)

日本は豊かで関係ないと
思っているとしたら、それは大きな間違いです。
絶対的貧困と相対的貧困
貧困状態を表す指標として、
「絶対的貧困」と「相対的貧困」がありますが、
この相対的貧困率が日本は先進30か国中、下から4番目!
ちなみに、相対的貧困率とは、国民所得の中央値
の半分未満の所得しかない人々の割合ですが、
日本は15%(約7人に一人)が相対的貧困家庭です。
※具体的な貧困ラインは、
総務省・全国消費実態調査では 135 万円(2009 年)、
厚労省・国民生活基礎調査では 122 万円(2012 年)。
大きな格差の中で、教育や様々な体験・挑戦
をする機会がなかなか得られず
苦しんでいる人も多いのです。
どんな人が多いかというと、
・高齢者世帯が多い
・単身世帯と一人親世帯が多い
・国民生活基礎調査において、郡部・町村居住者が多い。
という調査結果が出ています。
相対的貧困を減らすには
相対的貧困と働く場との関係は密接です。
一人でも働ける人が、働ける場を作ること
自体が国内相対的貧困を減らす
本質的な活動だと考えます。
・様々な事情のある人が働ける
ダイバシティ経営・職場の実現
・事業成長を通して職場を創造する
・群部・町村に魅力的な職場をつくる
・家庭でもできるテレワークベースの
小さな仕事創造・・・
すべて国内の相対的貧困を
減らすことにつながります。
他には、「子ども食堂」というような取り組みも
日本の各所で広がっています。
「子ども食堂」は、子どもやその親、
地域の人々に、無料or安価で栄養のある
食事や温かな団らんを提供する社会活動です。
こういった活動に参加する、応援するのも
立派な貢献になるかと思います。
とはいえ、まずは本業で、素敵な職場、
働く機会をたくさんつくること、
これが一番と私は考えます。
あなたの職場が多様な人を受け入れられる
素敵な職場になり、お客様・社会から
応援され成長すること、そのものが
日本の相対的貧困を減らします。
私も微力ながら、支援者として
頑張っていきます!
SDGs Goal.1「貧困をなくそう」で出来ること(国際編)

貧困状態を表す指標として、
「絶対的貧困」と「相対的貧困」がありますが、
この相対的貧困率が日本は先進30か国中、
下から4番目。
もう一つの絶対的貧困はどうか?
毎日の衣食住にも事欠くような
「絶対的貧困」を世界銀行では
2015年に1日1.90ドルを国際貧困ラインとしました。
仮に、1ドル110円とすると、
1か月30日として3300円で暮らして
いる人が沢山います。
ユニセフの調査によると今も、
推定6人に1人、世界で3億5,600万人の
子どもたちが、新型コロナ以前に、
極度の貧困の中で暮らしているそうです。
コロナで大変な思いをしている人も
いると思いますが、この子どもたちは、
コロナ以前の話です。ましてや、
今はコロナでさらに悪化している
可能性もあります。
絶対的貧困をなくすために
そんな絶対的貧困などの貧困を
なくすために、経済面でどんな
ことができるのか?
例えば、フェアトレードというものがあります。
コーヒー豆を例に取ると、
コーヒーの生産国のほとんどは、
いわゆる開発途上国といわれる国々です。
遠く離れたマーケットの状況は分からず
業者と十分に交渉も出来ない生産者の方は、
生産や生活に必要な利益を得られず、
不安定な生活を余儀なくされている事があります。
そんな状況を防ぐために、
開発途上国の農産物や製品などを、単に
市場価格で買い付けるのではなく、
農家の生活が成り立つように考慮した
フェア(公正)な価格で輸入・消費する
貿易のしくみがフェアトレードです。
フェアトレードについて詳しく知りたい方は、
https://www.fairtrade-jp.org/about_fairtrade/
を見てください。
単に安いものを仕入れるのでなく、
こういったフェアトレードの商品や材料
を積極的に使うことが貧困を減らす
一助になるのではないでしょうか?
私はモンゴルとスリランカの
子供たちのチャイルドスポンサーに
なって、毎月、気持ちばかりのご支援
をしています。
ご興味ある方は、一緒に歴史的に
大恩あるスリランカの子供たちを
支援しませんか?
SDGs Goal.2「飢餓をなくそう」で出来ること
SDGsへの取り組みは、持続可能な社会を
未来の子供たちに残す事業者・大人の
責務の一つです。
そして大企業よりも中小企業の方が
一歩踏み出すことはずっと簡単です。

Goals2「飢餓をゼロに」で
できることを考えたいと思います。
日本では生活習慣病が問題ですが、
世界では飢餓で苦しんでいる人が
たくさんいます。
日本のフードロス(廃棄食糧の)総量は、
国連の総食糧支援量より多い
というとんでもない話も聞いたことがあります。
経営以前に、一人ひとりが、
食べれないほど買わない、
食べ物を残さないということを
意識したいものです。
賞味期限は、消費期限とは違う
ので賞味期限1日オーバーくらい
は普通に食べましょう!
▼賞味期限と消費期限の違い▼
日本もったいない食品センター
https://www.mottainai-shokuhin-center.org/column/?gclid=CjwKCAjwj6SEBhAOEiwAvFRuKBzzOv-KhezeCSxHLX6mUqXtnn6XfonW2D2dorUEQjaBblO-Pq38DhoCrzEQAvD_BwE
事業面でも、無駄な食材を廃棄しない
事業展開や社員食堂運営も出来ます。
テーブル・フォー・ツー
企業も一人ひとりも、できる取り組みとしては、
テーブル・フォー・ツーという取り組みもあります。
▼テーブル・フォー・ツー▼
https://jp.tablefor2.org/
例えば無印良品の「Cafe&MUJI」でやっています。
以下、サイトから抜粋します。
“TABLE FOR TWO”は直訳すると
「二人のための食卓」です。
先進国の私たちと開発途上国の子ども
たちが食事を分かち合うというコンセプト。
世界の約75億人のうち、約10億人が飢餓や
栄養失調の問題で苦しむ一方で、
20億人近くが肥満など食に起因する
生活習慣病をかかえています。
TABLE FOR TWO(TFT)は、世界規模で
起きているこの食の不均衡を解消し、
開発途上国と先進国双方の人々の健康を
同時に改善することをミッションに活動しています。
先進国で1食とるごとに 開発途上国に1食が
贈られる TABLE FOR TWO(=TFT)
プログラムでは、肥満や生活習慣病予防
のためにカロリーを抑えた定食や食品を
ご購入いただくと、1食につき20円の寄付金が、
TFTを通じて開発途上国の子どもの
学校給食になります。
20円というのは、開発途上国の
給食1食分の金額。
先進国で1食とるごとに開発途上国に
1食が贈られるという仕組みです。
抜粋ここまで。
これに企業として参加したり、
テーブル・フォー・ツーに参加している
企業で食事をとることで、子供たちの飢餓
を減らすことに微力ながら関わることが
できます。
SDGs Goal.3「すべての人に健康と福祉を」で出来ること

今日は、Goals2「すべての人に健康と福祉を」で
できることを考えたいと思います。
今日は世界視点から。
世界で5歳未満でなくなる子供、幸いにも一昔前
よりは減ってきていています。
しかし、2019年で未だに520万人が、5歳未満で
亡くなっているのが事実です。(国連調査)
日本に生まれた時点で、相当に恵まれている
ことを自覚せずにはいられません。
身近な人は大丈夫だからといって、
それで良しではあまりに寂しいので、
自社で出来ることあれば、
やっていってはどうでしょうか?
食品や福祉にかかわる企業が、
その本業を通して世界で事業
を展開して、「すべての人に健康と
福祉を」を直接的に貢献していく
のはもちろんですが、
直接的につながらない会社でも
できることは、あります。
例えば、会社のクレジットカードで
たまったポイントの一部をSDGs3に
かかわる活動の応援に充てるなども可能です。
一人ひとりがペットボトルのキャップを
集めることで、ワクチンに繋げている
会社もあります。
ここで、大切なのは、その意義を社員に周知し、
自分達の活動が何につながっているのか?
なぜやっているのか?納得して、
共感して、取り組んでもらうことです。
(これは、わが社で働く、
働き甲斐にもつながります)
ある会社は、サイトには、
こんなことを書いてありました。
『そのリサイクルで発生した利益を
発展途上国のワクチン代として
寄付する取り組みに参加しています。2020年11月末時点で4,171個の
キャップが集まりました。キャップは430個で10円になります。
ポリオワクチン1人分は20円。4,000個余りでようやく4人分のワクチン代
になりますが、飲み終えたペットボトルの
キャップをゴミとして捨ててしまうのではなく、
集めて渡すということだけで、
子どもたちの命を助けることができます。』
私たちも、私たちなりに大変かもしれない。
しかしそれでも、遠い知らない世界のこと
ではなく、そういった地域の見知らぬ人にも
思いを馳せて出来ることをしていく。
これが日本人として大切にしていく
べきことではないでしょうか?
SDGs Goal.3「すべての人に健康と福祉を」で出来ること

Goals3「すべての人に健康と福祉を」で
できることを考えたいと思います。
今日、自分達の足元から。
仕事は、自分も他人も幸せにする活動ですが、
健康を害しては幸せになれません。
健康経営
経産省では「健康経営」
というものを提唱しています。
ーーー経産省のサイト引用ーーー
「健康経営」とは、
従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、
戦略的に実践することです。企業理念に基づき、従業員等への
健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等
の組織の活性化をもたらし、
結果的に業績向上や株価向上に
つながると期待されます。https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei.html
健康経営銘柄というものも
指定しており、「健康経営優良法人」
は中小企業も取得できるもので、
2021年4月時点で7935中小法人が取得しています。
この認定を取るために健康経営に
取り組むというのは本末転倒ですが、
何から手をつけていいか?という方は、
こういったものに取り組むことも有効と考えます。
(採用にもプラスになります)。
もちろん、自社ですぐにできることは
他にもたくさんあります。
体の健康もありますが、
心が病むと体も病みますので、
ここでは心の面にフォーカスを当てます。
第一歩は「一緒に働く仲間の悪口を言わない」。
程度低いと思われるかもしれませんが、
では絶対にないか?といわれると自信ない
所の方が多いのではないでしょうか?
その人のいないところの悪口も回り回って、
その人に届きます。
また人の悪口を聞かされた人も、
自分も言われているように潜在的に
感じるものです。
これでは、心の安寧はもたらされません。
全員で出来る取り組みなので、
是非してほしいと思います。
第二歩は、仲間の頑張り・取り組みに
光を当てて称賛する取り組みです。
ありがとうを伝える「ありがとうカード」、
お客様アンケートに名指しで喜びの声が
あった人を朝礼で表彰、
それぞれの頑張りに光を当てるアワード制度。
こんな仕組みがなくても、いつも、
「ありがとう」「〇〇さんのおかげ」
こういった言葉が飛び交う社風があれば、
心の健康の輪が広がりますね。
個々の取り組み方法やポイントなど
関心ある方は、個別にご相談ください。
SDGs Goal.4「質の高い教育をみんなに」で出来ること

Goal.4「質の高い教育をみんなに」で
できることを考えたいと思います。
今日は世界編です。
教育格差が経済格差を
生んでいるという側面があります。
知識社会になるにつれ、この格差は
大きくなっていく一方ではとも思います。
教育以上の未来への投資はない
のではないか?とさえ思います。
今日は、日本に居ながら、
世界の教育に貢献できる活動を2つほど紹介します。
ワールド・ビジョン・ジャパン、ルーム・トゥ・リード
私はWVJ(ワールド・ビジョン・ジャパン:)
という国際NGOの活動に参加しています。
具体的には
モンゴルのエンブスドちゃんと、
スリランカのタリーシャ君
(共に日本でいう小3くらい)の
チャイルド・スポンサーをやっています。
最初に始めたエンブスドちゃんとは、
もう5年くらいになります。
エンブスドちゃんには一度、
モンゴルまで会いに行きました♪
今TOP画面には「コロナ」のことが
記載されていますが、物の援助よりも、
教育のサポートを通して自立できる
地域を作っていくという考え方に
共感してやっています。
自分の子供にいい教育をと思うのは親心ですが、
一歩広げて、世界の子供たちにもできることしませんか?
会社の何からの活動の一部を
こういった支援に充てることも出来ます。
スリランカは今も募集中。私と一緒に
スリランカの子供たちを応援しませんか?
https://e-garyu.info/world/
▼ルーム・トゥ・リード▼
https://japan.roomtoread.org/
これは元マイクロソフトの
ジョン・ウッドという人が立ち上げたNGOで、
途上国に図書館を立てたり、
本を送るといった活動をしています。
その中の「ブックバンドプロジェクト」
というのは、参加しやすいように思います。
内容は、会社にあるビジネス本やDVDなど
で使わなくなったものを、
ルーム・トゥ・リードに送るというものです。
(社員の方が自宅から自宅の本を送ってもOK)
捨てずに、世界の子供たちのために活かす
ということで、こういった活動への参加も素敵だと思います。
なんでも経済に結び付けるのも嫌ですが、
あえて経済面・経営面でいえば、
こういった営利以外にも取り組む企業への
共感度は、若い優秀な人ほど高いと思います。
こういった活動をしている企業同士の方が
共感性もってコラボしやすいようにも思います。
これからの時代、価値観がより重要になって
くるので当然といえば当然かもしれませんね。
ものの順序は大切ですが、一応申し添えます。
SDGs Goal.4「質の高い教育をみんなに」
で出来ること 国内編

Goal.4「質の高い教育をみんなに」で
できることを考えたいと思います。
昨日に引き続き、今度は、国内で
教育に対して何ができるか?
ということで4つ触れたいと思います。
私自身は「志授業」というものに取り組んでいます。
『「子供は未来からの使者」、
これはインドの詩人タゴールの言葉です。
今までは高度成長もあり、日本はどちらかというと
私ファースト、自社ファーストの傾向が
強かったのでは?と思います。
しかし、それでは未来が立ちいかないことは
明白です。「未来ファースト」、20年後、
100年後に日本に生まれる子ども達に
胸の張れることをしていく必要があると思います。
その一つがこの志授業で、小中学生が
「自分の人生は自分で決める」という
『意思決定』のスタートラインに立つ支援を
することだと思っています。
いい大学を出て、いい会社に入って…
そんな紋切り型のキャリアプランが幻想
であることを皆が心のどこかで分かって
いながら、親子がその呪縛から離れられない
のは、子供に自らの未来を意思決定する機会
が少ないからです。
「自分の個性を活かして、一番たくさん
ありがとうがもらえる、自分だけのお役立ち山
を見つけて発表する」授業を、
地元兵庫県にも広げようと活動しています。
全国でやっています。
ご興味ある方はお声がけください。
企業自身が本業に関係する分野で、
子供たちに学びを提供することも出来ます。
一緒に「人が輝く会社づくり勉強会」を
開催させていただいている「長坂養蜂場」さんは、
採蜜体験教室をやっておられます。
「世界の食料の9割を占める100種類の作物種
のうち、7割はハチが受粉を媒介している」
(国連環境計画(UNEP)アヒム・シュタイナー事務局長、2011年)
と言われているように、人の大切なパートナーです。
単に採蜜を楽しむだけでなく、
生態系・いのちや自然の大切さを学べる活動です。
▼バンダイ「おもちゃで学ぶ出前授業」▼
https://www.bandai.co.jp/csrkids/school/
出前授業というものも全国各地で
行われていますね。
各社固有のお役立ちを子供たちに
伝えるということは身近にできる活動です。
たとえばバンダイさんは、
おもちゃで学ぶ出前授業プログラムをされています。
自社ならではの出来ること、ありませんか?
従業員の皆さまの働き甲斐にもつながります。
何より大切なこと
そして、何より私が大切だと
思っていることがこちらです。
「お父さん・お母さん自身が仕事の意義や
やりがいを子供たちに語ってやること」です。
仕事の中には大変なこと、
辛いこともあるかもしれません。
しかし、それをそのまま子供たちにぶつけては、
「大人になりたくない子供たち」が増えるばかりです。
「お父さん・おかあさんのように、
早く大人になって、多くの人を笑顔に
できる人になりたい!」そう思える家庭の
会話でありたいものです。
またそんな会話が自然と生まれる会社づくり
をしていきたいものです。
子供が将来に志を持ち、その実現に
勉強が必要となれば、勉強も勝手にするでしょう。
これが本来の勉強ですよね♪
(私も試行錯誤中ですw)
SDGs Goal.5「ジェンダー平等を実現しよう」で出来ること

Goal.5「ジェンダー平等を実現しよう」で
できることを考えたいと思います。
2019年12月世界経済フォーラムが発表した
「Global Gender Gap Report2020」で
男女格差を図るジェンダー・ギャップ指標
が発表されていますが、日本は153か国中121位です。
▼内閣府 男女共同参画局のサイト▼
https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2019/202003/202003_07.html
まだまだ働く女性の活躍は少ないといえます。
労働人口が大きく減少していく日本にあって、
価値観が多様化していく現代にあって、
多様な視点を経営に活かすことはとても重要です。
ブランディングの観点でも重要な一貫性・言行一致
ブランディングの観点でも、
一貫性・言行一致がとても重要です。
例えば健康食品の会社が不健康の巣窟
では説得力ないですし、
お作法の教室の先生が
口汚い人だったら誰も教室に入らないでしょう。
女性の意見が大きく反映される
商品・サービスを提供している会社に
女性が全然いないと、
やはりうまくいかないでしょう。
優秀な女性社員が欲しい!といいながら、
女性が活躍する素地がなければ、
誰も採用試験受けてくれないでしょう。
現代の仕事において、男性でなくては
出来ない仕事というのはほとんどないでしょう。
育児中や介護中でもテレワークも
簡単にできるようになりました。
(当社はずっと育児中のお母さんに
テレワークでサポートしてもらってます)
もちろん、男女を問わず、
働くことへの意欲や覚悟には
個人差があります。
それはフラットに評価すれば良いですが、
男性だから、女性だから、〇〇だから、、、
と先入観で採用や処遇するのは
非常にもったいないですね。
そもそも、男性が・・・女性が・・・と
2つで考えるのも適切でないかもしれません。
LGBTQについての認知も広がってきました。
LGBTQの、仲良しだからといって
「どんな男性が好き?」「どんな女性が好き?」
と聞くと、悪気はなくても傷つけて
しまっていることもあるかもしれません。
こういったことを、
一つ一つ社内で学び・考えていくことが、
ジェンダー平等、誰もが活躍できる
社会づくりにつながります。
まだまだ発展途上の日本の現状では
マイノリティー属性の優秀な人を
惹きつけ・活躍してもらえる会社は、
発展する大チャンスだと思います。
(追伸)
私は、結果合わせの悪平等には反対です。
活躍できる機会・活躍しやすい環境の平等が大切、
そういう考え方を前提としてお伝えしています。
SDGs Goal.6「安全な水とトイレを世界中に」で出来ること

Goal.6「安全な水とトイレを世界中に」で
できることを考えたいと思います。
一昔前は、
「安全と水はタダと日本人は思っている」
という話がありました。
安全について、このご時世でそんな事を
まだ言っている人はいないと思いますが、
水はまだまだ関心が薄いかもしれません。
私が子供のころは、水をお店でお金だして
買うなんて信じられませんでした。
トイレも、ぼっとん便所を知らない人や
知っていても使えないような人も
増えてきているかも知れませんね。
しかし、自分の日常がそうだからといって、
自分さえ今困っていなければよいと、
周りに無関心でいることは、非常に無責任
なことのように思います。
▼世界資源研究所、世界の水リスク地図2019年版を発表▼
https://water-business.jp/article/201911027/
世界資源研究所(WRI)は、世界の人口の4分の1が
非常に高い水ストレスに直面しているとする
2019年度版の『アクエダクト世界水リスク地図を発表。
アクエダクトは189の国と地域を、旱魃リスクや
川の洪水リスクなど13の指標をもとに
ランク付けを行い、その結果をウェブ上で
インタラクティブに公開している。
世界の人口の約4分の1が住む厳しい水ストレス
に直面している17ケ国では、農業、工業、都市により、
利用可能な地表水と地下水の毎年平均80%が
使用されている。
この数字は気候変動により今後一層悪化することが予想されている。
(以上、上記サイトより引用)
今でさえ、そうですが、
これから世界中で開発や経済発展が進みます。
人口も増え続けます。
結果、ユネスコは2050年までに世界人口の
半分が水不足になると予測しているのです。
日本も無関係ではありません。
水が戦争や紛争を生む可能性もあります。
水不足が食料不足につながることもあります。
そうすると、輸入が止まったり、
海外拠点の業務が止まったりするかもしれません。
「日本は水が豊富だから大丈夫」
という意見の人もいるかもしれません。
しかし日本の水が大丈夫なのは、
「大量の食料を海外から輸入しているから」
という事情があるからです。
あるセミナーで聞いたのは、国内だけで
やりくりしようとしたら、日本が7.7個
必要とのことでした。
世界全体が平均的に豊かになっていく
未来(これ自体はよいこと)において、
これからは「金を出したら買える」
という傲慢な考えは通用しないかもしれません。
どの国も経済が成長した先で、自国民を
飢えさせてまで輸出しないと思うからです。
つまり決して他人事ではないということです。
他人事では居られないのです。
大きな社会課題は大きなビジネスチャンス
でもあります。
水源管理、水質改良、淡水化技術、
水を効果的に管理する仕組み、節水技術、
これらはすべて大きなビジネスに
成長するチャンスがあります。
世界にたくさん貢献できるからです。
貢献できる会社が成長するのは、
当たり前のことです。
そこまでは難しくても、
例えば、身近な水を大切にすること
から始めてもいいですし、
水に関する支援をしている会社の
製品・商品などを積極的に使うこと
でも貢献できます。
また災害時などは国内でも
水の問題が発生しますね。
BCP(事業継続計画)の中で、
水やトイレの問題を織り込んで対策
しておくのも良いでしょう。
自社だけでなく、何かあったときに、
水やトイレで地域に貢献できることも
計画的に取り組めばできるでしょう。
このSDGsシリーズ全般の共通テーマ
でもあるのですが、
問題意識の広さ・深さ・強さは、
事業にイノベーションを起こす
チャンスにもなります。
そういった観点でも、煽るつもりは
ありませんがSDGsを通して、
危機の共有と、三方未来よし経営のヒント
を一緒に考えていければ幸いです。
※余談ですが、
ユダヤ人があれだけ優秀で成果を
出すのは、おそらく遺伝子よりも、
危機意識・問題意識の強さに起因している
ように思います。
日本人は戦後、どうもそのあたりが
ダメになってしまっている気がします。
SDGs Goal.7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」で出来ること
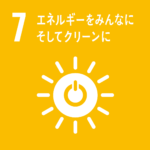
SDGsへの取り組みは、持続可能な社会を
未来の子供たちに残す事業者・大人の
責務の一つです。
そして大企業よりも中小企業の方が
一歩踏み出すことはずっと簡単です。
今日は、Goal.7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」
で、できることを考えたいと思います。
日本はなんと、この分野で2019年12月
国際的な会議で表彰されています!
会議は、COP25(国連気候変動枠組条約第25回締約国会議)
日本が受賞したものは、化石賞(Fossil Award)です!
しかも2回目の受賞です!
喜べません・・・
化石賞は、駄作映画に贈られるラジー賞や
愚かな死因に与えられるダーウィン賞と同じ
皮肉を込めて授与される大変に不名誉な賞です。
▼世界いろいろ雑学ランキング(外務省のサイト)▼
https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/co2.html
ここにはCO2排出量の世界ランキングが
載っていますが、中国が2位アメリカを
ダブルスコアで引き離す圧倒的1位ですが、
日本も世界TOP5のランカーです。
(中国が化石賞を受賞していないところは
いろいろな事情があるのでしょう…)
日本は、今でも一次エネルギーの約80%が
化石燃料です。
逆に優等生はウルグアイ。
国全体をほぼ100%再生可能エネルギーで
対応しているそうです。
そして、世界の経済発展と人口増で
EIA(US)予測では、2050年までに+50%の
エネルギー生産が必要になるとされています。
そんな中で、企業に何ができるか?
再生可能エネルギー供給、
効率的なエネルギー管理システム、
省エネの暮らし・仕組・商品・サービス、
これらはすべて大きなビジネスに成長する
チャンスがあります。
もちろん、世界にたくさん貢献できるからです。
私がTOPと直接個別にお話したこと
のある2社を例に挙げます。
自然電力は2011年6月設立なので、
もうすぐ10歳になる若い会社です。
東日本大震災をキッカケとして
私とほぼ同年代の3人で
立ち上げられた会社です。
何回かZOOMで2人でお話していて、
素晴らしいな♪と思うのは、
発電から利用までだけでなく、
電気の地産地消や、それとリンクした
地域活性化、地域ブランド創造など
一面的でない取り組みを私心なく
取り組まれているところです。
草創期に、理念で世界2位の
再生エネルギー企業と
コラボしたりもされて
未来の社会づくりに取り組まれています。
各社が取り組みやすいペースで
自然由来の電力を購入できる
プランを提供されています。
自然電力の電気を取り入れることも、
各社で出来る取り組みなので、
是非お勧めしたいと思います。
▼日本環境設計▼
https://www.jeplan.co.jp/
岩元会長のお話を聞き、
とてもしびれました♪
この時のお話は、2019年12月9日の
メルマガに書いたので、
そちらも是非読んでほしいのですが、
会長の言われたミッションは、
「地上資源経済圏をつくり、
戦争・テロも無くす。」
というものでした。
たしかに、地下資源「石油」などで
戦争や紛争は多いです。
▼2019年のメルマガ「大きな絵を描く、語る、巻き込む」▼
https://s-kando.com/archives/2443
こちらの記事も面白いです。
▼デロリアンを古着で走らせた!?▼
https://plus.paravi.jp/business/002727.html
こういった会社がもっともっと
日本から生まれれば♪と思います。
一方で、上記2社のようなことはできない!
と思われる方も多いと思います。
しかし、間接的に貢献できることは
たくさんあります。
・自然電力の電気を購入する
・有休の土地を発電等に活かす
・地産地消を進め、物流エネルギー
を最小化する。
・簡易包装にする
・ペーパーレスを進める(素材から出力、
廃棄まで多くのエネルギーが使われています)
・電気をこまめに消す
・クールビズ、ウォームビズ
・一人二人で車のらず電車利用
個人で出来ることも、
会社でできることも、山ほどあります。
損得、好き嫌いだけでなく、
地球や世界のためにできることを
出来ることからやっていきませんか?
ちりも積もれば・・・です。
SDGs Goal.8「働きがいも経済成長も」で出来ること

SDGsへの取り組みは、持続可能な社会を
未来の子供たちに残す事業者・大人の
責務の一つです。
そして大企業よりも中小企業の方が
一歩踏み出すことはずっと簡単です。
今日は、Goal.8「働きがいも経済成長も」
で、できることを考えたいと思います。
コロナもあり、AI革命もあり、
同一労働同一賃金の推進、
働き方革命、人生100年時代の働き方と、
働き方の大変革期に差し掛かっている
ことは、誰もが感じていることだと
思いいます。
ここでは、短中期的に確実にやってくる
AI革命の観点で、「働きがいも経済成長も」
考えたいと思います。
AI革命を端的に感じられるサービス
として、「Google Duplex」があります。
「Google Duplex」はAIが実店舗や
予約センターに電話をかけて、
人間を相手に会話をし、予約を取り、
その結果を報告してくれます。
まるで一昔前のSF映画のようなサービスです。
お店側がAIで受けることも出来る模様。
▼「Google Duplex」の動画▼
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=14264
AIの自然言語処理ロジックは進化する
一方で、文脈理解が進み、長く複雑な文章
も対応できるようになりました。
今後も、進化することはあっても、
悪くなることはありえません。
私なんかは、英語の習得はあきらめて
AIの進化にかけているタイプの人間ですので、
うれしい要素の方が多いですが、
「働く」という観点では、
そう簡単なことではありません。
AIがほぼ人間並みにやってくれる。
会話がそうなると、単純なPC作業の置き換え
など、ごくごく簡単なレベルの話です。
故に、AI革命によって、
・決断し責任を負う仕事
・クリエイティブな創造的仕事
・肉体的な仕事(ロボットより人が安いもの)
だけになってしまい、二極化が
進むのでは?という話もあります。
こんな時代に、
さて人は何をすればいいのか?
働くというのは、お金を稼ぐ以上
の意味があります。
人にしかできないことは何か?
また、あえて人がやってこそ
素敵なことは何か?
を各社で考えていく時代だと思います。
私は、少なくとも、「働き甲斐改革」は
各社取り組む必要があります。
皆がそれぞれの個性と長所を活かして
・人でしか出来ないこと
・人がやった方が素敵なこと
をやっていくためには、
「働き甲斐」「主体性」がマストです。
仕事はもともと、
「自分も他人も幸せに、
未来も豊かにする活動」です。
経済成長のために働きがいを
何とかするというのは本末転倒で、
「働き甲斐と成長」を両輪で回したいものです。
そのために、どんなことができるか?
これについては、私の本職でも
ありますので、今後もメルマガの
中で折に触れて発信していきますが、
皆さまも是非考えてみてください。
SDGs Goal.9「産業と技術革新の基盤をつくろう」で出来ること

SDGsへの取り組みは、持続可能な社会を
未来の子供たちに残す事業者・大人の
責務の一つです。
そして大企業よりも中小企業の方が
一歩踏み出すことはずっと簡単です。
今日は、Goal.9「産業と技術革新の基盤をつくろう」
で、できることを考えたいと思います。
日本は、特に製造業については、
世界TOPレベルの産業基盤を
有する国だと思います。
一部の領域だけ強い国は他にもありますが、
業界の範囲、裾野の広さは、
素晴らしい数々の中小企業が活躍
していることで明らかです。
そんな日本で、「産業と技術基盤
と言われても・・・」と思われるかも
しれませんが、
まだまだ未開の技術、未成熟の技術
はありますし、それを開発することは
日本だけでなく世界への貢献になります。
自社の技術を一歩前に進める。
これ自体も、基盤充実になります。
勿論、縮小日本にとどまらず
世界に出ることを通して、
世界の技術基盤を底上げするという
ことも素晴らしい貢献です。
特別な誰かへの貢献ということでなく、
自社を一歩前に進めることを
通して、貢献するという発想が大切です。
また「産業の基盤」を広くとらえると
その産業を魅力的にする、
憧れの業種・業態・職業にする
ということも大切なことですね。
業界地位の向上というと堅苦しいですが、
要はブランディングです。
ブランドができることで、
・いい人財を採用しやすくなる
・定着率があがる
・働く人が、より誇りをもてる
・多くの人に知ってもらえる
・新規顧客獲得コストが下がる
・売上が増える
・リピートが増える
・販売コストが下がる
・利益率があがる
・他社とコラボしやすくなる
などなど、多大なメリットがあります。
自社のブランディングは、
日々の仕事を通してやっていく
仕事の中核的テーマの一つですが、
自社だけでなく、業界の地位
自体をあげることも、一緒に出来ないか?
追加できないか?
業界でなく、地域の魅力をアップする
という考え方も出来ます。
例えば、食品製造業であれば、
地元食材・産品を使った
魅力的な商品を開発、販売し、
ヒットさせれば地域のブランディング
に貢献もできますね。
もっとすぐできることで、
最近取り組まれているところも
多いこととしては、
ユニフォームをカッコよく刷新
することも効果的です。
女性がおしゃれをすると元気に
なるように、カッコいいユニフォーム
の方がやる気わきますよね。
周りから見ても、
ボロボロ・ドロドロの服より
かっこいいし、業界イメージも上がります。
私のご縁のある企業様では、
社外の場やイベントなどで
スーツ等を着る時に、
ネクタイだけお揃いにしている
会社もあります。
大勢が同じネクタイしており
一体感を感じます。
考えだすと、できることは
たくさんあります。
自社の目の前の仕事から、
一つ視野を広げて、できることを
考えてみましょう♪
これは、もちろん、自社の成長発展
にもつながります♪
SDGs Goal.10「人や国の不平等をなくそう」で出来ること

SDGs Goal.10
「人や国の不平等をなくそう」
で、できることを考えたいと思います。
このテーマは、
他のテーマともオーバーラップ
してくるようなテーマですね。
そこで、17のテーマにぶら下がっている
169のターゲットを見てみると、
10.2『2030年までに、年齢、性別、障害、
人種、民族、出自、宗教、あるいは
経済的地位その他の状況に関わりなく、
すべての人々のエンパワーメント、
および社会的、経済的、および
政治的な包含を促進する。』
というものがあります。
これをもとに、中小企業でもできる
ことを考えてみます。
これ、経営面で一言でいえば
『ダイバーシティ経営』ですね。
性差で機会の不利益が生じない
ようにすることは勿論、
障がいを持つ人でも、
働ける職場づくりもあります。
これから外国出身の方が
就職されることも増えてくるでしょう。
その時に、言葉や風習の壁で
彼ら彼女らが必要以上に苦労しない
ような工夫も必要です。
多様性を活かすことが出来れば、
やもすると同質的で固定的な
社内に新しい風を吹き込み、
事業革新のキッカケが生まれます。
「現状維持は衰退」の現代において
ダイバーシティ経営の推進は、
SDGsを考えなくとも大切ですね。
また、これはお客様にも
言えることです。
多様なお客様に喜んでいただける
商品・サービス・接客などが
できれば、お客様が増えるわけ
ですから売上・利益も増やせますね。
そう考えると、やれることは
本当に沢山あります。
皆で働く仲間の国の言語や
手話の勉強をするのも
よいでしょう。
ピクト・アイコンを使い、
言葉に頼らずともある程度
分かるように工夫することも出来ます。
ユニバーサルマナー検定
というものもあります。
▼ユニバーサルマナー検定▼
https://universal-manners.jp/curriculum#section03
やれることから、
一つずつ取り組んでいきませんか?
SDGs Goal.11「住み続けられるまちづくり」で出来ること

SDGs Goal.11
「住み続けられるまちづくり」
で、できることを考えたいと思います。
これは地域密着の中小企業で
やりやすいテーマです。
対応する169のターゲットには、
一部抜粋すると以下のようなものが
列挙されています。
・世界の文化遺産及び自然遺産の
保護・保全の努力を強化する。
・災害による死者や被災者数を大幅に削減
・女性、子供、高齢者及び障害者を含め、
人々に安全で包摂的かつ利用が容易な
緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。
・災害に対する強靱さ(レジリエンス)を
目指す総合的政策及び計画を導入・
実施した都市及び人間居住地の件数を
大幅に増加させ、仙台防災枠組2015-2030
に沿って、あらゆるレベルでの総合的な
災害リスク管理の策定と実施を行う。
いろいろ考えられそうですね。
例えば、
誰でも過ごしやすいという観点で、
ハンデのある方向けの駐車スペース
やアプローチの改善も出来ます。
楽しい街づくりという観点で、
私が訪問したことのある、
ある地方の企業では、
自社駐車場で地域住民を
巻き込んだBBQ大会をやっていました。
美しい街づくりなら、
植栽や休憩スペースなどが街に
憩いの場を作り出しますし、
環境負荷を押さえたイルミネーション
などもきれいですね。
会社周辺の地域清掃なども
地域に根差す企業として
地元に愛されることも含め
一石二鳥ですね。
災害対策では、緊急時の自動販売機
や食品在庫などの解放、
緊急時グッズや避難場所の提供
などもできるかもしれません。
これからは、自社のBCPの観点
でも考えておきたいことです。
自動車関係の会社なら、
安全なモビリティ社会づくりの
安全教室などもいいかも
しれませんね。
住み続けられる街があってこそ、
その街で事業が続けられます。
地域への責任としても、
具体的にできることを
やっていきたいものです。
※補足:仙台防災枠組2015-2030
第3回国連防災世界会議で採択されたもので
SDGsのように2015年から
向こう15年を見据えた枠組みです。
▼内容はコチラ▼
https://jcc-drr.net/projects/sendai-framework/
SDGs Goal.12「つくる責任つかう責任」で出来ること

SDGs Goal.12
「つくる責任つかう責任」
で、できることを考えたいと思います。
今回も、いくつか169のターゲットを
抜粋で確認してから、私たち一人ひとりや
中小企業にできることを考えて
いきたいと思います。
ーーー該当ターゲットの一部ーーーーー
天然資源の持続可能な管理及び
効率的な利用を達成する。小売・消費レベルにおける世界全体の
一人当たりの食料の廃棄を半減させ、
収穫後損失などの生産・サプライチェーン
における食品ロスを減少させる。製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な
化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、
人の健康や環境への悪影響を最小化するため、
化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。
他にもありますが、ターゲットまで
見るとより具体的にイメージしやすい
かと思います。
Reduce Reuse Recycle
関連して、多くの人が聞き覚えの
あるキーワードとして3R
「Reduce Reuse Recycle」という
ものがあります。
これは順番が大切で。
減らす→再利用する→リサイクル
の順番でやりましょうということです。
ペットボトルを例にとると、
以下のようになります。
Reduce
そもそもペットボトルを
使わない。
Reuse
同じペットボトルを
水筒替わりに何度も使う
Recycle
資源ごみとして捨てて
別の形で使う。
まず、そもそも使う量を減らせないか?
という観点で、企業の立場であれば、
・簡易包装にする
・売り切れる分だけ販売する
など考えられます。
欠品は機会損失という考え方
もありますが、一日100食限定の
売り切り型にした京都の「佰食屋」
さんのようなモデルもアリです。
何でも拡大がいいとは言えません。
▼佰食屋 Webサイト▼
https://www.100shokuya.com/about/
消費者としては、
・簡易包装を希望する
・食べきれないものは頼まない
・不要不急、あればいい
レベルのものは買わない
なども出来ますね。
一見すると経済活動にマイナスの
インパクトがあるように感じますが、
そもそも、多ければ多いほど良い、
という考え方時代から決別が必要
なのかもしれません。
ちなみに、日本のフードロスは
とんでもないレベルです。
2020年4月の農水省の資料によると、
廃棄物処理法における食品廃棄物は
食品関連事業者で752万トン
(内、可食部分328万トン)
一般家庭で、783万トン
(内、可食部分284万トン)
合計で食品廃棄物1,535万トン、
食品ロス612万トンとのことです。
これは世界全体が援助している
食料の量の約2倍に相当、
廃棄コストは年間2兆円にも
及ぶそうです。
なんという環境負荷、
なんという経済非効率、
そして飢えている人達への
間接的な攻撃でしょうか?
企業の立場でいえば、
本当に必要なものだけ仕入れ、
本当に必要とされる分だけ売る
ということが大切ですね。
勿論、間接資材についても同様です。
環境整備・5Sで無駄なものの
購入を減らすことも出来ます。
また、同じものを買うのでも、
環境負荷の低いものを選ぶという
ことも大切な視点です。
地産地消は、運送コストなどを
抑える意味でも理に適っています。
さらに、以前ご紹介したことがある
産業廃棄物中間処理業の石坂産業では、
「つくる責任、つかう責任」
にプラスして、「捨てる責任」を
掲げておられます。
▼石坂産業の関連メルマガ▼
https://s-kando.com/archives/3726
ライフサイクル全体を見て、
自分達にできることを
考えていきたいものです。
SDGs Goal.13「気候変動に具体的な対策を」で出来ること

SDGs Goal.13
「気候変動に具体的な対策を」
で、できることを考えたいと思います。
気候変動については、
「温室効果ガスを減らす」が
一つのキーワードになります。
端的に一つ上げれば、
CO2 二酸化炭素です。
どうすればにCO2が排出されるか?
を考えてみると、
・火力発電でCO2排出
→電気を使えばCO2が出る。
・内燃機関を使うとCO2排出
→車に乗る
→長距離輸送
・モノを作るときに電気利用
一例としてアルミ製品。
アルミは精錬に大量の電気必要。
リサイクルで何と97%も電気節約。
・冷暖房・照明も電気利用
・ごみ焼却でCO2排出
・呼吸をしてもCO2出ますが、
これは仕方ないですね(笑)
CO2というと、どうしても
車のイメージがありますが、
電気自動車ならエコか?と言われると
発電がエコでない場合が大半なので、
そんなに単純な話ではありません。
・・・余談・・・
諸説あるのと、私も専門家ではない
ので確たることは言えませんが、
エンジン車は×、電気自動車が〇と
単純に信じるのは、思慮が浅いと思います。
個人的な直観では、現状なら
エンジンを発電に100%回して、
発電した電気で走らせるのが
一番環境負荷低いのでは?と
想像しています。
電気は特性上、安定貯蔵が難しく、
送電ロスも大きく、発電も現状は
CO2排出型か原子力が殆どだからです。
・・・余談ここまで・・・
基本は3R、特にReduceの視点
基本は、昨日も書いた3R、
特にReduceの視点が大切と考えます。
会社で出来ることで
考えられることを列挙してみます。
・クールビズ、ウォームビズ
・1名2名で車に乗らない。
・そもそも無駄な移動はしない。
テレワークは、とても有効。
・小まめな消灯
・地産地消、旬の食材を利用
・無駄なものを買わない
・廃棄ロス
商品やサービスの原材料調達から
廃棄・リサイクルに至るまでの
ライフサイクル全体を通して排出される
温室効果ガス排出量をCO2換算して、
商品やサービスに分かりやすく表示する
カーボンフットプリント(CFP)プログラム
への参加も一つの方法ですね。
▼CFPプログラム▼
https://www.cfp-japan.jp/beginner/
未来のために、多少コストが上がっても、
ブランディングと共に
消費者の方に理解頂いて販売する。
また、無駄を減らして、利益率を高める。
環境対応=収益にマイナスとは
限りません。
出来る方法を考えていきましょう。
SDGs Goal.14「海の豊かさを守る」で出来ること

SDGs Goal.14
「海の豊かさを守る」
で、できることを考えたいと思います。
四方を海に囲まれた海洋国家・日本
で暮らし事業をする私たちには
とても大切なテーマですね。
突然ですが、
「海洋プラスチックごみの量が海にいる魚を上回る」
といったら信じられますか?
実は、2050年には海にいる
膨大な魚よりも、海の中のプラスチック
総量の方が増えるという予測が本当に
あるのです。
そして、日本はプラスチックの
生産量で世界第3位。
1人当たりの容器包装プラスチック
ごみの発生量については、世界第2位。
です。
海の恩恵をもらってきたことに
関して世界有数の日本は、
プラスチック大国でもあります。
▼詳しくはWWFのサイト参照▼
https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/3776.html#section3
プラスチックは分解せず、長い期間
蓄積し続け、生物の体にも入っていき
悪影響を及ぼすと考えられています。
日本の企業として出来る事は
多くあると思います。
例えば
プラスチック容器・
石油由来の包装を使わない
社内でペットボトルを出さない
同じプラスチック容器でも
ワンユースでなく、ずっと使える
ものにする。
家庭でも工夫できるよう
社内勉強会を開催
また、海の問題は、私たちが直接出して
いるプラスチックに限りません。
間接的に海の環境・豊かさに
マイナスのインパクトを与えてる
ことがあります。
何気なく買って食べている魚介類。
これも、近い将来、多くの魚介
海産物が食べられなくなるという
予測もあります。
つまりサステイナブル(持続可能)で
ない海産物を大量に輸入して、
そのうち多くは、フードロスで廃棄
したりしています。
IUU漁業という言葉もあります。
Illegal, Unreported and Unregulated漁業、
つまり、「違法・無報告・無規制」な漁業
のことです。これが大きな国際問題に
なっています。
▼IUU漁業のレポート▼
https://www.wwf.or.jp/activities/data/20171227_ocean02.pdf
グルメもたまにはいいですが、
こういった事実にも目を向けて、
できることを考えていくことが
大切だと思います。
社食のあるところなら
食材に留意する
海に流しているものに
どんなものがあるか調査し
見直してみる。
食品加工業なら仕入の
内容を吟味する。
海の豊かさを考える勉強機会をつくる
目の前の危機になってからでは遅いことです。
また、目の前の海が仮にきれいでも、
何気ない生活や事業推進で、遠く外国の
海を汚していることもあります。
時間軸・空間的広がりにおいて、
自分が直接的に関係なさそうであれば
それでOKというのは、あまりに
無責任なことと思います。
できるところから、やっていきましょう。
SDGs Goal.15「陸の豊かさも守ろう」で出来ること

SDGs Goal.15
「陸の豊かさも守ろう」
で、できることを考えたいと思います。
2050年、海の生き物より、海のプラスチック
の方が多くなるという恐ろしい話を
SDGs ゴール14で触れましたが、
陸も多くの危機があります。
世界人口 約78億人、
そして、日本を含む一部の国が
豊かさを享受するのでなく、
世界中が豊かになろうとしている。
更に人口はますます増え続ける。
地球のサイズは変わらない。
どう想像しても、エネルギーも
食料も、物品の材料も、
厳しい未来しか想像できません。
有名なReduce・Reuse・Recyleの3R
(減らす、再利用する、再資源化する)
の中でも減らすが何より重要です。
最近は、Refuse(買わない)の単語を
加えた、4Rというものもあります。
・Refuse(買わない)
・Reduce(減らす)
・Reuse(何度も使う)
・Recycle(最悪、再資源化する)
本当は「買わない」が圧倒的に重要
なのだと思います。
作る・運ぶ・売る・買う・捨てるのサイクル
を前提とする経済システム自体が
もはや限界なのだと感じています。
それを前提としないビジネスモデルへの
転換が企業の社会的責任のような気が
最近しています。
FSC認証
さて、「陸の豊かさ」で私が一番に
思い浮かぶのが、FSC認証です。
私は前職で印刷会社に勤めていたので、
このFSC認証は10年以上前から
普通にしっていました。
FSC認証は、森林の環境保全に配慮
しているものにつけられる認証です。
印刷会社では、紙を大量に使います。
お客様企業に多少高くても、
FSC認証の紙を使いませんか?
と提案するのです。
余談ですが、海のエコラベルとしては
MSC認証というものがあります。
▼MSC認証▼
https://www.msc.org/jp
こういったFSC認証の紙を使うという
のも一つの方法です。
他には、
他にも、木材を使う場合に、
間伐材を積極的に活用。
会社の敷地を緑で豊かにする
(ストレス軽減効果も)
グリーンウォールをつくる
(夏の温度を下げるので、電気も
節約できる)
なども出来ます。
森林以外にも出来ることはあります。
私はお肉好きなのですが、
ベジタリアンの人は環境に優しいです。
草うしは一頭が成牛出荷されるまでが
約26ケ月らしい(黒毛和牛は38か月)ですが、
26か月の肥育で3.5トンの牧草を食べるそうです。
この牧草や飼料をつくるのに、
大きな環境負荷がかかっています。
世界全体として豊かさが進むにつれ
食肉の問題も出てきます。
私はベジタリアンは少しきついので、
自然に近いお肉を少量だけ、時々頂く形に
していければいいなと思っています。
すべてを一気にすることは、
難しいと思いますが、個人でも会社でも
できることから、やっていきましょう!
SDGs Goal.16「平和と公正をすべての人に」で出来ること

今日は、SDGs Goal.16
「平和と公正をすべての人に」
で、できることを考えたいと思います。
169のターゲットでは、
・あらゆる場所で、あらゆる形の暴力と、
暴力による死を大きく減らす。・子どもに対する虐待、搾取、人身売買、
あらゆる形の暴力や拷問をなくす。・各国でも、国際的にも、法律にしたがって
ものごとが取りあつかわれるようにし、
すべての人が、平等に、争いを解決する
ための裁判所などの司法を利用できるようにする。
といったものが続きます。
ちなみに、ユニセフの調査によると
世界のどこかで、5分に1人、子どもが
暴力によって亡くなっているそうです。
▼ユニセフの該当ページ▼
https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/17goals/16-peace/
子供に対する虐待などは残念ながら
存在しますが、世界的に見れば、
統計的に見れば、日本は本当に
恵まれていると言ってよいです。
(勿論、だから少数を切り捨てて
よいという話ではありません)
さて、評論家をしていても仕方ない
ですが、現状認識は大切なので
お伝えしました。
ここからは、一人ひとり、
中小企業で取り組めることを
考えていきたいと思います。
当社は直接は関係ないから…
という姿勢は、私は賛同しかねます。
勿論、恵まれない国、厳しい国
に対して、寄付をしたり、
その国の産業基盤に資すること
をすることは、素晴らしいことです。
それ以外に、
身近な日本をもっと平和に
精神的に豊かな国にして、
世界のお手本になるということも
できることではないか?と思うのです。
イライラや怒りが、暴力を生み、
日本でも(厳しい国から言えば
贅沢な話かもしれませんが)
平和が脅かされています。
例えば、中学校などのカツアゲ。
(私も昔、返ってこないお金を
少し貸したことあります。)
や、陰湿ないじめなどを見て見ぬふり
する教師や親は最低ですね。
地域で働く中で、そういった子供たち
を見つけた時に働きかけてあげる、
職場が緊急避難先になって
あげることもできるかも知れません。
例えば、あおり運転。
あおり運転から暴行事件などに
なるケースもあります。
あおり運転が馬鹿らしくなる
バンパーステッカーを張っている
人もいますね。
社用車にそういったステッカーを
張るなども小さな出来る事です。
例えば、職場内のギスギス。
陰口・人格否定・陰謀・押し付け・
パワハラ・モラハラ・・・
なんでも病名をつけることには
反対ですが、心の病気で働きたく
ても働けない人も増えています。
「陰口はやめましょう」といっても
なかなかなくなりません。
それよりも、よい習慣を上書き
する方が効果的ですね。
ありがとうカード、ヒーローインタビュー
アワード・表彰など、プラスの
空気が流れる取り組みを増やす
ことが効果的です。
ビジネス的にも平和は大切です。
平和で、安全・安心・ポジティブな
社風の会社は、これは断言できますが、
生産性があがります。
そして日本中の企業が、笑顔あふれる
平和で公正な職場になれば、
日本全体も、もっともっと世界の
お手本になることが出来ると信じています。
「身近な平和と公正」にも
目を向けて、やれることから
やっていきましょう。
SDGs Goal.17「パートナーシップで目標を達成しよう」で出来ること

このゴール17だけ、他のSDGsのゴールと
少し毛色が違います。私は実現に向けた
憲法のようなものだと思っています。
この緊急だけれど壮大な課題に対して
一人では解決できない。
バラバラでは解決できない。
だからパートナーシップというわけです。
17番目のゴールに対応するターゲット
を読んでみると「途上国への支援」など
も多いのですが、以下のような内容もあります。
・科学技術やその知識を、
抱え込まずに共有しよう
・WTOのもとで、
公平で開かれた貿易体制を
・すべての国が協力して、
世界経済を安定させよう
・SDGs達成のために、一貫性のある政策を
・SDGs達成のために、
国ごとのやり方を尊重しよう
・多種多様なパートナーシップで、
SDGsを推進しよう
・その際、最も効果的なパートナーシップ
をみつけ、推進しよう
以上の言葉は、SDGs169ターゲットアイコン
日本版制作プロジェクトから引用しました。
ターゲットアイコンまで踏み込むことで
より具体的に取り組みの目的を明確化
できますね。
▼SDGs169ターゲットアイコン日本版制作プロジェクト▼
https://www.asahi.com/ads/sdgs169/result/
共有、公平、開かれた、協力、一貫性
尊重、多種多様、効果的な
などのキーワードが、パートナーシップ
の方針として感じられます。
パートナーシップの力を使えば、
経営資源が相対的に劣る中小企業
でも可能性は無限大です。
たとえば、超零細企業である当社でも
パートナーシップの力で、SDGsに関連
して色々な取り組みが出来ています。
正直なところ、当社完結でやっている
ことは一つもありません(笑)
▼当社のSDGs関連の取り組み▼
https://s-kando.com/about/sdgs
ビジネス的に言えば、
自社のSDGsの取り組みと他社の取り組み
のパートナーシップが、将来の事業コラボ
につながることもあるかもしれませんね。
SDGsにも出来るところから積極的に
取り組む「三方未来よし経営」の会社が、
世界を救うと本気で思っています。
一緒に、やっていきましょう!
SDGs Goal.18???
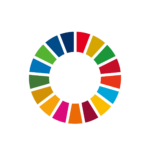
最後に、SDGs Goal.18のご提案です。
昨日までで、SDGsのゴール1~17
について、個人事業主でも中小・零細企業
でも、取り組めそうなことを中心に
触れてきました。
・自社さえよければいい。
・やりたい会社がやればいい。
・直接的に利益になるかどうか?
が判断基準
こういう考え方は、自社すら
中長期的には上手くいかないと思います。
実際、目先の何か?を期待するのでなく、
企業の本分や責務に立って、
積小為大・凡事徹底で取り組めば、
それは共感の波紋の一滴になりますし、
ブランディング・採用・コラボ等にも
プラスに働くはずです。
個人や中小零細でも無力ではありません。
微力はあるのです。
さて、こういった取り組み、SDGsの
17ゴール、169ターゲットに則って
取り組むことは、とても素晴らしいと
思うのですが、
さらに主体性・オリジナリティを発揮
してみるのはどうでしょうか?
名づけるならば、
「勝手にSDGs ゴール18」
自社・お客様・パートナー・社会・未来
を見た時に、もっと自社らしいゴール
があるかもしれません。
我が社の働く仲間と一緒に、
またはパートナーも巻き込んで、
「勝手にSDGs ゴール18」
を作って、発信して、皆でイキイキ取り組む。
そんな活動も素敵だなと
SDGs連載を続ける中で感じました。
私も考えてみます。
