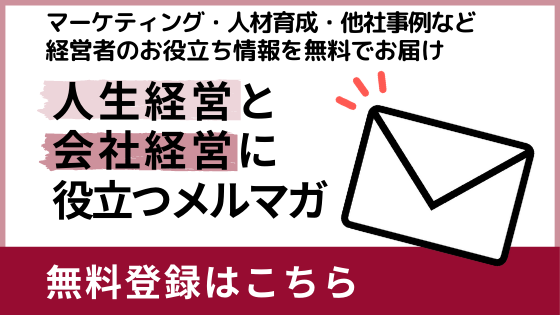「下請法」が進化 名称変更へ!
従来の「下請法」の正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」と
いいます。少し長い名前ですね!
この法律は「下請事業者に対して、決められた期日までに
適正に代金を支払いましょう」というルールを
定めたものです。
要するに、下請事業者を守るための重要な法律です。
昭和31年に制定された歴史ある法律でもあります。
法律の条文を紐解いてみると、
第1条(目的)には次のように記載されています:
「親事業者は取引を公正に行い、下請事業者の利益を
保護しなければならない。」
この法律では、下請事業者(仕事を受ける側)には
特別な義務が課されておらず、親事業者が守るべき
ルールのみが定められています。
そのため、大手企業の調達担当者(物を買う人たち)は、
この法律を守ることについて非常に気にしています。
むしろ、下請法を恐れています。
エピソード1 「取引先にて」
5年程前のある日、調達担当者が取引先を訪問した際、
取引先の社長の机上に「下請法」に関する
テキスト(冊子)が10冊以上積まれていたそうです。
その光景を見た調達担当者は、値下げ交渉を
切り出すのをためらってしまったのだとか。
エピソード2 「行政官庁からの調査依頼対応」
忘れもしません。私自身の話ですが・・・
10年ほど前の話ですが、ゴールデンウィーク連休前に
下請法の関係官庁から連絡が入り、その対応(調査)で
連休が3日間つぶれたことがありました。
エピソード3 「調達担当者の苦悩」
実務上の話です。
下請法自体はシンプルで分かりやすい内容ですが、
とすると「解釈が難しい」場面が出てきます。
そんなとき、
コンプライアンス上問題がないかの確認のためです。
このような調達担当者の姿勢から、
下請法を重視する理由
「下請法」がこれほど重視される理由は、違反すると
「勧告」を受ける可能性があるからです。
「勧告」が新聞などで公表されることは、
勧告の件数は令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)は
21件となっています。
私が公取のHPで調べた限り平成23年以降 最多の件数です
以下は直近の勧告件数の推移です:
・平成23年(18件)から平成27年(4件)まで徐々に減少
・平成28年(11件)で一時的に増加
・その後、令和3年まで低水準(約5件)で推移
・令和5年(13件)と令和6年(21件)では再び増加
特に令和6年には件数が大幅に増加し、
全体として減少から増加への転換が見られます。
これらの統計資料は毎年5月末ごろに
公正取引委員会から公式に発表されます。
法改正の動き
そんな「下請法」ですが、
2025年3月11日に閣議決定され、
新名称は次の通りです:
「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の
遅延等の防止に関する法律」(37文字)
またまた長い名前になりましたね!
このように新名称への改正の動きに見られるように、
法律は時代に応じて進化していきます。
この下請法は中小企業を守る法律です。
中小企業は法改正の趣旨・目的を理解し、
下請法および新たに改正されるポイントを
具体的に把握することで大企業と向き合い
公正な取引を実現する機会だと考えられます。
(参考資料:改正法案の概要について)