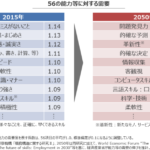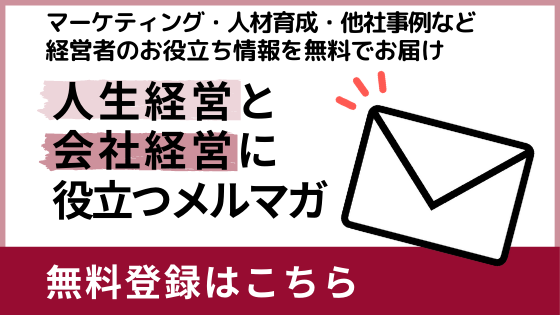議題・問いの質が成果を決める(RPG発想法合宿より)
先週の土曜日・日曜日に、
ラテラルシンキングのために私と仲間で開発した
RPG発想法(R)認定ファシリテーターの
一泊二日の合宿を開催しました。
一言でいえば、超リラックスした空気で、
非常にレベルの高い学びと、
仲良しになれました(堅く言えば人間関係構築)。
合宿の内容
1.場づくり手法の共有と体感
2.議題の設定方法の研究ワークショップ
3.議題の価値を本質レベルで高める方法の体感型ワークショップ
4.宴会
5.人柄が出る 人狼ゲーム
6.RPG発想法を使ったワークショップ
前号では「場づくり」について
少し触れましたが、
今号と次号で「議題づくり」について
触れたいと思います。
質問です。
みなさんは、会議やミーティングで
議題の設定にどれだけ注意を払っていますか?
「問いの質」が「アウトプットの質」に
直結するのは有名な話です。
問い(議題)を変えると、アウトプットも変わる
というシンプルな例を示します。
例えば、ある健康食品を販売する部門
の会議での議題を考えてみます。
議題A
・なぜ売上が上がらないのか?
アウトプットA
・新商品を出せていないから
・販売力が弱いから
議題B
・どうすれば、売上が上がるか?
アウトプットB
・新商品の開発を進める
・お客さまの声や実績を訴求する
議題C
・どうすればリピード購入が増えるか?
アウトプットC
・継続的に採ることの価値を伝える
・定期購入システムを導入する
・ポイント制度を導入する
課題Aは、
出来ない理由がたくさん出てきそうです。
現状把握と原因究明は勿論大切なのですが、
最終的に欲しいものは原因把握ではないはずです。
メイン議題としては微妙ですね。
課題Bは、
テーマが大きすぎるので、
大枠の解決策が中心に出てきそうです。
それが悪いわけではないのですが、
具体的なアクションにはつながりにくそうです。
課題Cは、
ある程度、考えるべきことが明確になっていて、
具体的な対策までの道筋は近そうですね。
どれがいい、悪いということでなく、
問いでアウトプットが変わると言うことを
よく理解して、議題設定する必要があるということです。
更に言えば、問いの質、議題設定が上手い人は、
課題解決が上手い、アウトプットも秀逸な
傾向がつよいと思います。
合宿でやったのは、生成AIなどで出てきにくそうな
発展的・開発的・探索的なアイデア創出なので、
その前提で、どのような問いが適切なのか?
についてワークショップ形式で皆に考えてもらいました。
問いの内容(上記の課題例A、B、Cのような内容)は
勿論のこと、「言葉のチョイス、表現方法」でも
参加者の頭の使い方がかわり、アウトプットが
変わるよねという対話が生まれていました。
例えば、「離職率について」という議題の場合、
離職率について、勿論減らしたいということは
何となく分かるのですが、どんな方向性で考えればよいのか
人によっていろんな解釈がでてしまいます。
結果、議論が曖昧になりがちです。
「離職率について」という議題だと、
アウトプットは、
・離職率の推移をしらべるべきだ
・離職率の高い部署とその特徴を調べよう
といった、自分事でないものが
出てくる可能性があります。
「後ろ向きな離職を減らすために、
私たちにできることは何か?」
だと、自分が出来ることを考えよう!
という気持ちが生まれますし、思考も
そちらに向かっていきますね。
内容としては同じでも、伝え方、表現、
言葉のチョイスで、主体的な空気になったり
他人事的な空気になったり、
話が概念的になったり、具体的になったり
簡単にしてしまいます。
議題設定で、成果が全く変わるとしたら、
議題設定はもっと時間と注意を払って
やっていきたいですね。