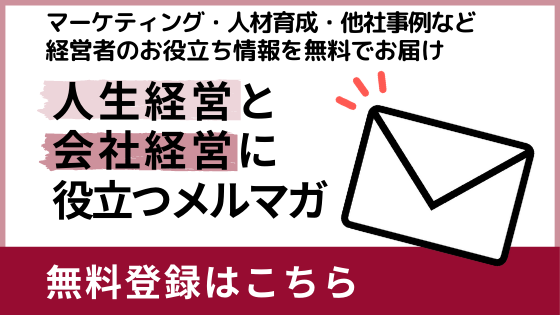3年以内の離職率:約35%
チームSKM 吉田 理です
毎年10月頃、厚生労働省から
「新規学卒者の離職状況」が発表されます。
最新の調査によると、2021年(令和3年)
の大学新卒者の3年以内の離職率は34.9%であり、
過去15年間で最も高い水準となっています。
ただし、2000年~2005年の間も35%超を
推移していた時期があり、決して例外ではありません。
この離職率に関するデータは昭和62年以降
公開されており、一貫して30%前後を推移している状況です。
また、大学新卒者の離職率が注目されがちですが、
実際には高卒者の離職率の方がさらに高く、
平均で4割前後、多い時には5割を超えることもあります。
この統計結果から、新卒者の一定数が3年以内に
離職することは「一般常識」として
捉えられる傾向があるのかもしれません。
しかし、企業にとってせっかく採用した人材が
教育の成果を発揮する前に退職してしまうことは、
採用コスト・育成コストの観点からみても大きな損失となります。
その要因は何か、抑止策はあるのか、改めて考えてみましょう。
離職理由と若者の特徴
離職理由については、この統計資料では
具体的に記載されていませんが、
別の厚生労働省の調査によれば主に以下の要因が挙げられます:
- 労働条件への不満(給与が低い、労働時間が長いなど)
- 仕事上の過度なストレス
- 会社の将来性や安定性に対する不安
- リアリティショック(採用時の理想と現実のギャップ)
また、早期離職する若者には以下の特徴が指摘されています:
- 相談できる相手がいない
- コミュニケーション能力の不足
- 自己理解の不足
- 人間関係の問題
抑止策について
一方で、企業にとって早期退職者の存在は
依然として大きな損失であるため、
以下のような施策が重要視されています:
- 職場への適応を支援する取り組み (入社後のフォロー)
- 若者のストレスを察知する上司の能力向上 (管理職の育成)
- 公正な人事評価制度の導入 (評価の仕組みの構築)
- 中長期的な視点に基づく育成プランの策定 (CDP制度の導入)
- 1on1ミーティングを通じた信頼関係の構築
実践すべき具体的施策
早期退職を防ぐには、若者の特徴を理解し、
日常的に抑止策を考えることが欠かせません。
経営者の皆さんは、どのような取り組み
を実践し、仕組み化していますか?
採用時のミスマッチを防ぐ施策や労働条件の改善が
最重要課題と言えますが、実現には困難が伴います。
それ以外にすぐに取り組むことができる
施策としては、
例えば:
- 職場になじめない社員への声掛けを経営者自らが実践する
- 朝礼や職場懇談会、ランチミーティングを定期的に開催する
- 1on1ミーティングを導入し、傾聴を重視する
(従業員の話を9割、管理職側は1割程度の姿勢で耳を傾ける)
これらのコミュニケーション活性化施策を
取り入れることで、企業ごとの状況に応じた
柔軟な改善が可能となります。
ぜひ実践を検討してみてください。
ちなみに私の経験談を一つだけ・・・
採用時のミスマッチを防ぐために、
私は人事担当時代、パートの採用を任せられていましたが、
(累計数100名以上)
入社してもすぐに退職される抑止として、
採用時の説明は厳しめに説明していました。
現場で説明するとき アッセンブリ(組立作業)ですが、
「見かけよりしんどいです」等・・・
もちろん魅力あるようにも説明し バランスよく工夫をしてました。