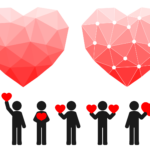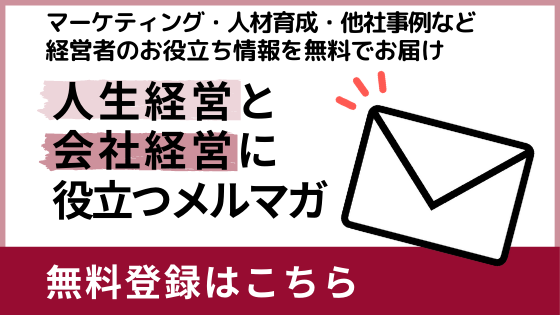「流暢性(りゅうちょうせい)」押さえてますか?
突然ですが、皆さまのお店や会社の商品・サービスは、
お客様にとって「わかりやすい」でしょうか?
実は、この「わかりやすさ」こそが、
今の時代、お客様に選ばれ、愛されるための、
ものすごく大切なカギになっています。
今号は、マーケティングの世界で「流暢性(りゅうちょうせい)」
と呼ばれる、この「わかりやすさ」について、
そしてそれを意識した経営がいかに重要かをお話しさせてください
■まず、「流暢性」って何でしょう?
難しく聞こえるかもしれませんがシンプルです。
流暢性とは、
お客様が、商品やサービスの情報に触れた時に、
「あ、これ分かりやすいな」
「スッと頭に入ってくるな」
「なんか、いい感じだな」と感じる、
その“スムーズさ”のこと
です。
パッと見てわかるデザイン、
覚えやすい名前、
簡単な説明書、
直感的に使えるウェブサイト…
こういったものは「流暢性が高い」と言えます。
逆に、ごちゃごちゃして分かりにくい、
読むのが面倒、使い方が複雑… と
いうのは「流暢性が低い」状態ですね。
私たち人間は、流暢性が高いもの
(=スムーズに理解できるもの)に対して、
無意識に「良いもの」、「正しい情報」、「好き」
と感じやすいと言われています。
心理学では「処理流暢性効果」と言われます。
頭にスッと入ってくる心地よさを、
その対象自体の良さだと勘違いしてしまうんです。
これが、お客さまに選ばれたり、
従業員がついてきてくれたりする大きな理由の
一つになったりします。
※話が少し逸れますが、
逆に流暢性だけで安易に判断してしまう
人の脳の特徴を把握して、流暢性だけに
流されない人になることは、経営者・リーダー
として大切かとも思います。
流暢性の罠は使っても、使われるな!
です。
■商品における「流暢性」のある・なしの例
×流暢性がない場合(うーん…となりがち)な例
「分厚くて専門用語だらけの取扱説明書の家電」
せっかく買ったのに、読む気が失せて
結局基本的な機能しか使われない…
◎流暢性がある場合(おっ!いいね!となりやすい)
「イラスト中心、直感的に操作がわかるガイド付きの家電」
すぐに使えて、満足度もアップします。
箱を開けた瞬間の「これなら使えそう!」という感覚が大切です。
■サービスにおける「流暢性」のある・なしの例
×流暢性がない場合(面倒だな…となりがち)
「入力がやたら多く、どこに何を書くか分かりにくい予約画面」
途中で離脱されてしまう原因になります。
「オプションが複雑で分かりにくい料金体系」
お客様は不安になり、申し込みをためらってしまう。
「専門用語ばかりで、意味不明なスタッフの説明」
せっかく良いサービスでも、その価値が伝わりません。
◎流暢性がある場合(スムーズ!イイナ♪となりやすい)
「必要最低限の入力、ガイドも親切な予約画面」
ストレスなく予約完了でき、良い体験のスタートになります。
「松・竹・梅」のように、一目瞭然な料金表」
お客様は安心して比較検討できます。
「お客様の目線で、丁寧・分かりやすいサービス説明」
納得感と信頼感が高まり、購入につながります。
サービスは形がないからこそ、余計に、申し込みから利用、
アフターフォローに至るまでの体験全体が
「スムーズでわかりやすい」ことが、重要ですね♪
■「わかりやすさ」を追求する経営を!
お客様は日々、情報の嵐の中で生活しています。
その中で、選んでもらうために、
「わかりやすい」
「簡単」
「スムーズ」
といった流暢性の高さが、強力な武器になります。
流暢性を意識することで、
・お客様のストレスを減らして満足度を高める
・「いいよ♪」「分かりやすいよ」という口コミにつながる
・お客様の早い購買につながりやすくする
・誤解による購買と、その後のクレームを減らせる
といったメリットに直結します。
もちろん、わかりやすさだけを追求するあまり、
商品の本質的な価値やサービスの深みが失われては本末転倒です。
しかし、
「どうすれば、もっとお客様にスムーズに価値を届けられるか?」
という視点を持つことは、これからの経営で、
ますます重要になってくるはずです。
ぜひ一度、お客様の気持ちになって、商品やサービス、
ウェブサイト、パッケージ、店舗、説明資料などを
見直してみましょう。
「もっとわかりやすくできる部分はないか?」
「もっと快適にできないか?」
「ストレス源はないか?減らせないか?」
その問いかけが、事業の繁盛、
お客様とのより良い関係づくりの第一歩になると思います。
私も「さんよし会」や「ベンチマーク研修会」
分かりやすくするように努力して参ります。