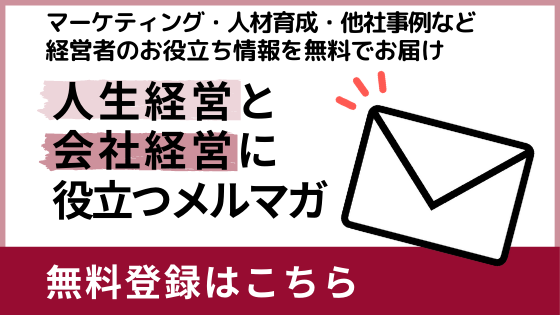強調月間の活用でマンネリを打破 企業文化の醸成
経営コンサルタントの吉田です。
皆さんの会社では、国や行政が実施している「〇〇強調月間」や
「〇〇週間」に合わせて、具体的な取り組みを行っていますか?
例えば、以下のようなキャンペーンが毎年実施されています。
(政府広報オンライン等より一部抜粋)
・全国交通安全運動(4月・9月)
・熱中症予防強化キャンペーン(4/1~9/30)
・禁煙週間(5/31~6/6)
・全国安全週間(7/1~7/7)
・防災週間(8/30~9/5)
・健康増進普及月間(9月)
・全国労働衛生週間(10/1~10/7)
・品質月間(11月)
・下請取引適正化推進月間(11月) など
行政がこれらの強調月間を設ける目的は、
啓蒙活動を通じて意識向上を促し、
労働者の行動変容を実現するためです。
いわば企業が活用できる「キャンペーン」のようなもの。
強調月間を効果的に活用することで、
新たな気づきを得たり、企業文化の醸成につながります。
強調月間の活動が形骸化していませんか?
しかし、こうした取り組みも年々形骸化してしまう
傾向があります。
例えば「全国安全週間」の場合、厚生労働省が
4月25日に要綱を発表しました。
ご覧になられましたか?
2025年の全国安全週間は、6月1日から6月30日までの
準備期間を経て、7月1日から7日まで実施されます。
この週間は、労働災害の防止や安全の意識の高揚を目的として、
昭和3年から毎年実施されています。(今年で第98回)
今年のスローガンは
「多様な仲間と 築く安全 未来の職場」
では、御社の安全週間はどのように実施されていますか?
単なる「お知らせ」に留まっていませんか?
社員が積極的に参加できる仕組みになっていますか?
成果を上げるための工夫とは?
私が実践してきたことには、安全週間を単なる義務ではなく、
既存の仕組みと如何に融合させながら効果的に
活用するかを視点におきました。
例えば、以下のような取り組みがあります。
・啓蒙ポスターの掲示(行政のポスター)
・トップメッセージの発信
・パンフレット・チラシの配布
・職場懇談会のテーマに設定
・KYT活動(リスク予測トレーニング)
・スローガン標語の募集
・改善提案制度の安全テーマ募集
・朝礼時の安全所感
・研修の実施(参加型ワークショップ形式)
・eラーニングによる教育
・安全パトロール
・安全表彰
・日々の実施事項カード(個人で決める)
こうした活動を通じて、単なる「お知らせ」ではなく、
社員の主体的な参加を促すことができるのです。
準備月間もうまく活用する必要もあります。
未来に向けての取り組み
「全国安全週間」に限らず、「コンプライアンス月間」、
「品質月間」、「交通安全運動」、「健康増進普及月間」など、
多くの強調月間があります。
各々に発出される官公庁の活動要綱を参考にしながら、
独自の啓蒙活動や意識向上施策を展開してはいかがでしょうか。
教育面においては、Eラーニングの活用が
一般的になっていますが、
ワークショップ形式の参加型研修も重要視されています。
単なる義務感や受け身ではなく、社員が主体的に関与できる
仕組みこそが、マンネリを打破し、社員の意識をさらに
高める肝となるのです。
経営層やリーダーの皆さんの役割において、このような
取り組みをどう活用し、企業文化に根付かせていくか
が大切です。
ぜひ、アイデアを出し合いながら、自社独自の工夫を
取り入れ、強調月間を効果的に活用してみてください!