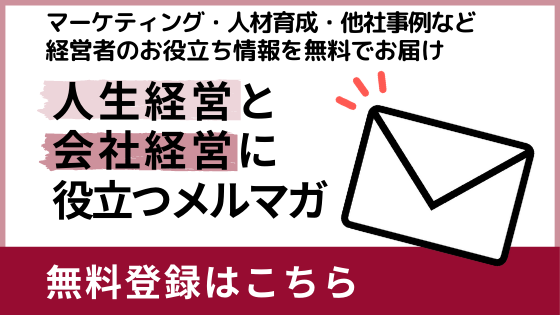ボトムアップの組織変革の一歩は読書会!?
チームSKM 上村です。
トップダウンではなくてボトムアップで
組織を変革していくための方法として
「勉強会」がおすすめです。
勉強会の方法も色々な方法があると思いますが
読書会はラクラク学びや気付き
そして実践につながりやすい方法です。
今回は読書会の形式と
その手順、適したケース
利点、野球について
まとめましたので参考にしてみてください。
読書会の形式と方法
1)共通の本を読む形式
参加者全員で同じ本を読み、感想や学びをシェアするスタイル。
昇進者
- 読む本を決める(ビジネス書、専門書、成功事例の本など)
- 事前に読んでもらえる または 章ごとに読んでディスカッション
- それぞれの学びや気づきを共有し、業務への対話方を話し合う
適したケース
- 企業文化や価値観を共有し、言っていきたい。
- 共通の知識を備え、組織力を高めたい
いいね
- 全員が同じ知識を得られる
- 一体感のある生まれる
- 知識が業務的に話しやすい
ライン
- 参加者興味にばらつきがあるとモチベーションが下がる
- 読書量が負担になる可能性がある
2)それぞれが読んだ本を紹介する形式
参加者がそれぞれ異なる本を読んで、コンテンツを共有するスタイル。
昇進者
- それぞれが自由に本を選ぶ
- 読むだの概要、学び、活かせるポイントをプレゼンする
- 他の参加者とのディスカッション、考察
適したケース
- 多様な視点を得た
- 各自の専門分野の知識を持ちたい
いいね
- 短時間でたくさんのエッセンスを学べる
- 参加者の自主性を高めやすい
- 読書の負担が軽い
ライン
- 共有される内容の質がばらつく
- 受けやすい興味が薄い内容だと参加して努力が落ちる可能性がある
- ある程度の方向性を示さないと「勉強」という形にはならない
3)章ごとに投稿して読む形式
1冊の本を複数人で分担して読み、それぞれの部分を要約・発表担当するスタイル。
昇進者
- 本を決め、それぞれが担当する章を割り振る
- 担当者が要点をまとめて発表
- 全体で議論し、全員で内容を理解する
適したケース
- 長めの専門書や論文を扱う場合
- 読書の負担を軽減しつつ全員の知識を増やしたい
いいね
- 1冊を短時間で勉強する
- 負担が分散される
- 参加者の意識協力が高まる
ライン
- それぞれの結論の仕方に差が出る
- 自分で1冊読むよりは本の理解や知識の習得はおちる
4)読みながら議論する形式
その場で本を少しずつ読み進め、ポイントごとに議論する形。
昇進者
- その場で本を読み進める(事前に読む必要なし)
- 重要な部分が出てきたので議論する
- その場では原則的に、意見を交換する
適したケース
- 短めの本やエッセイ、論文を扱う場合
- 参加者の事前準備が不要にしたい
いいね
- 事前の準備が不要で気軽に参加できる
- その場で意見を考えられるので、ご理解ください
ライン
- 進行がスムーズでないといけない(進行役の力が重要)
- じっくり読めないため、理解が浅くなる可能性
読書会のメリット
- 知識の共有が進む:社員のスキルアップや業務改善につながる
- コミュニケーションの活性化:他配置との交流やチームワーク向上
- 継続的な学習の習慣がつく:学ぶ文化が社内に定着しやすい
- 業務への応用がしやすい:本から得た知見を実際の仕事に活かせる
読書会の扱いと注意点
- 参加者のモチベーション管理が重要:強制にならないよう、関心のある本を選ぶ
- 進行役が必要:司会・ファシリテーターを決める、議論が慎重になる工夫
- 負担を減らす工夫が必要:全員が負担なく参加できる形式を考える
- 業務との関連性を意識する:ただの雑談にならないよう、実践的な学びを意識する
成功させるためのポイント
- 目的を明確にする:何を得るための読書会なのか、明確なゴールを持つ
- 参加者の意見を尊重する:興味のある本を選ぶようにする
- 適切な頻度で実施する:負担にならないよう、月1回~隔週程度がベスト。時間も2時間/回くらい
- 業務との接続を意識する:実践につながる学びを得られるようにする
まとめ
読書会は、社内の学習文化を醸成し
社員のスキルアップとコミュニケーションの活性化につながる有益な取り組みです。
ただし、形式を間違えると「義務的」「負担が大きい」
などの対処もあります
目的や組織の特性に合わせて適切な方法を選びましょう。
ぜひ、自分に合った読書会のスタイルを見つけてください
楽しく学びの場を作ってみてください!