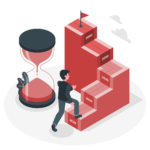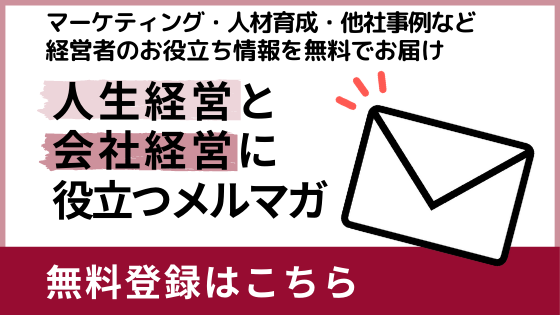読書スピーチのすすめ
上村さんが「読書会のすすめ」についての
内容をお伝えさせて頂きました。
それをうけて、読書会の一部とも言える、「読書スピーチ」
について、私からは触れたいと思います。
これは、私も実際に連続研修やコンサルにも
取り入れているもので、とても効果があるものです。
読書スピーチとは、本を読んで得た学びや感想を
言葉にし、他の人と共有する取り組みです。
話し手にとっては、思考の解像度に影響する語彙力
を高めることになりますし、自分の考えを整理し、
論理的に伝える練習にもなります。表現力も向上します。
聞き手にとっては、新たな視点や知識を得る機会
になるだけでなく、互いの意見を共有することで、
相互理解が促進されます。共通言語をもつことと、
相互理解によりチーム力が強化されます。
ただし、効果的な読書スピーチをするためには
押さえておきたいポイントもあるので、
お伝えします。
それは、単に本のあらすじを話すのではなく、
自分にとってどのような意味があったのか、
どの部分が心に残ったのかを掘り下げて語ることです。
例えば、ある本を読んで人生観が変わった、
新しい観点を得たといった体験を共有
することで、聴衆にも深い学びを提供できます。
読書スピーチに万人共通の正解はなく、
読み手の人生経験を本・読書を通して
伝えるとイメージすると分かりやすいと思います。
また、読書スピーチの準備ですが、
出来るならばした方が良いでしょう。
しっかり準備して、本番に臨めば、話す本人にとっても、
聞き手にとってもより価値あるものになります。
読書スピーチのやり方は色々アレンジできるのですが、
私は以下の2パターンでやることが多いです。
■ケース1:指定図書で実施
1)共通の課題図書を設定
2)準備では実践したいことも含めてもらう
3)4人程度のグループで、読書スピーチ
3−1)3分でスピーチ
3−2)スピーチしての本人の感想
3−3)聞いた人の感想やよりよくするフィードバック
3−4)次の人へ (一人トータル10分程度)
4)次回の時に、実践内容を報告
複数回やり定着するまでやることもある
こちらは、教育効果に意図をもって浸透させたい
時に有効ですね。リーダーシップ育成など
明確なテーマがある時によく使います。
■ケース2:自由図書で実施
1)自由に本を選んでもらう
2)準備内容もお任せ
3)4人程度のグループで、読書スピーチ
3−1)3分でスピーチ
3−2)スピーチしての本人の感想
3−3)聞いた人の感想やよりよくするフィードバック
3−4)次の人へ(一人トータル10分程度)
こちらは、人となりをお互いにしったり、
幅広く教養や語彙力を高めたい時に実施。
時間の関係で、各回1人のみの時もあれば、
全体で数人発表してもらうケースもあります。
読書スピーチは、自分の世界を広げ、
他者とつながるための素晴らしい手法です。
皆さんもこの機会に、ぜひ挑戦してみてください。