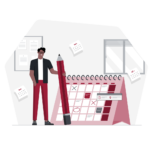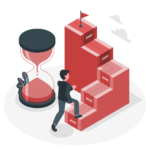若手育成、如何にして最低必要努力投入量を目指すか?
人財獲得競争の時代になり、
若手の定着と成長は、悩ましい問題です。
定着とも関係するのが、成長実感ですが、
ゆとり世代とかZ世代にどうすれば・・・
という話もよく聞きます。
しかし、私はZ世代は。。。的な安直な若者論
には否定的です。
実際は、色々な人がいる。
それが事実ですから。
中小企業で統計的に意味のある人数を
採用することもまずあり得ないと思います。
実際は、一人一人に向き合う。
それしかありません。
とはいえ、社会を取り巻く環境は大きく変わりました。
私のようなおじさんが若い頃にやったやり方は
できなくなりました。
私が若い頃は、とにかく、がむしゃらにやれ!
一々教えられない。見て覚えろ!盗め!
若い時の苦労は買ってでもしろ!
午前様上等!俺の若いころはAM3時くらいまで仕事してた。
努力・根性→その先の量質転嫁
(量をこなすことが質の変化を生む)
そんなところがありました。
少し極端に書いていますが、私が若手社員の頃、
確かに教えてもらえなかったし、
現場で痛い目見ながら覚えたし、
午前様は普通、21時からもうひと踏ん張り!
という具合で働いていた時期も結構長かったです。
それを全く恨んでいないし、
その時期があったから今の自分があるとも
思っていて感謝しているくらいです。
非効率だったと思いますが、
量質転嫁は確かにありました。
そして、これには一定の論拠もあって、
神戸大の金井教授の「最低必要努力投入量」や
マルコム・グラッドウェルの著書
『『天才! 成功する人々の法則』で広まった
「1万時間の法則」などは、量質転嫁と
大いに関連した話と言えます。
※最低必要努力投入量
ある分野で成果を出すために必要な最低限の努力量のこと。
目標達成や専門性の確立に一定以上の時間と労力が
必要であることを示しています。
※1万時間の法則
ある分野で卓越した技能を習得するには
約1万時間の集中的な練習が必要だとする考え方。
1日3時間の練習を続けると約9年かかる計算です。
しかし、それはもうできません。
働き方改革の流れの中で、労働力の流動性が
高まった世の中で「時間を使って何とかする」
という考えは非常に難しくなりました。
そこで必要なのが、どうやって、
「最低必要努力投入量」に早く到達させるか?
という議論になります。
努力投入量=「時間」×「時間当たり負荷」
なので、時間当たり負荷をどう高めるか?
ということを考える必要があります。
イメージで言えば、
我流でやる非効率な筋トレでなく、
トレーナーが見て科学的に効果的で、
高負荷な筋トレを短時間でやるイメージでしょうか?
この高負荷で高効率な筋トレ的な
メンバー育成で時短と成長を両立する。
これが、これからの若手育成のテーマ
になりそうです。
次号では、「時間当たり負荷」を高める
育成方法について考えたいと思います。