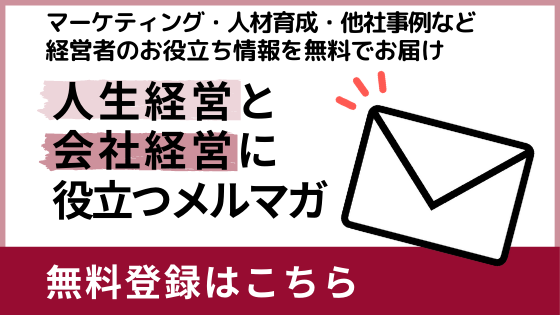Z世代と上手くやる!世代間ギャップ解消施策
チームSKM 佐々木千博です。
先日、他社でZ世代向け記事を依頼されて書いた
のですが、そこで使わなかった方の内容をお送りします。
そもそも、Z世代、Y世代と世代で一括りにせず、
一人一人に向き合おう!というのが本当の多様性を
活かす組織づくりというのが、私の基本スタンス
ではありますが、参考になることもあると思います。
ーーーー
Z世代という言葉はご存知でしょうか?
言葉は聞いたことがあるという方や、
最近の若者のことと大くくりで
考えられている方も多いかもしれません。
Z世代の明確で確立した定義はないのですが、
大凡1990年代半ば~2010年代序盤に
生まれた世代のことをZ世代といいます。
物心ついた時からインターネット等が身の回りにあり、
デジタルネイティブと言われる世代ですね。
ちなみに、Z世代の次は、α(アルファ)世代と言います。
2010年から2024年生まれで、
世界では約20億人に達し、
完全なるデジタルネイティブですが、高校卒業後に就職となれば、
後3年後には入社してくる方もいます。
私の娘と息子も完全にα世代です。
さて、私たちの職場にも、
Z世代と呼ばれる若手社員が増えてきました。
彼らは、デジタルに強く、情報感度が高く、
多様性を自然に受け入れる世代です。
一方で、経営者やマネージャーの多くは、
こう感じている人も多いようです。
「指示を待ってばかりで、自分から動かない」
「どんな言葉をかけたらいいかわからない」
「ハラスメントを気にしすぎて、厳しく言えない」
これを簡単に世代間ギャップとして片付けるのは早計です。
こうした戸惑いは、実は“世代間ギャップ”というより、
“価値観のズレ”から生まれています。
Z世代は「自分の人生を大切にしたい」
「無駄なことはしたくない」「意味のある仕事がしたい」という、
極めて合理的で、目的意識の高い世代です。
つまり、私たちがリーダーとして問われているのは、
「どうすればやる気を出すか」ではなく、
「彼らが意味を感じる環境をどう整えるか」なのです。
■ギャップを解消する7つの処方箋
以下では、Z世代と良好な関係を築き、
強みを活かすための「実践的ギャップ解消術」を7つ紹介します。
いずれも、現場ですぐに活かせる内容です。
1.「意味づけミーティング」で“仕事の意義”を共有する
Z世代は、「何のためにこの仕事をやるのか」
を理解できると、一気に動きが変わります。
単なる“作業”ではなく、“自分の役割”として
感じる瞬間がモチベーションの源です。
ある会社では、若手社員自らが「自分たちの働き方や社会貢献」を
テーマに討議する仕組みを運用しています。
月1回のディスカッションで、「この仕事は何の価値を生むか」
「会社の存在意義とどうつながるか」を話す時間を設けています。
(自社への展開例)
月初10分だけ「今月の仕事の意味」
「顧客への価値」や「メンバーの成長につながる点」
Z世代は“指示待ち”から“自分ごと”に変わります。
2.「こまめ具体的フィードバック」で信頼関係を築く
Z世代は“リアルタイムな言葉”を求めます。
年1回の評価だけでは「自分は見てもらえていない」と感じがち。
ある大手自動車会社では上司と部下が月1回の1on1を行い、
目標進捗や悩みを共有。「評価ではなく対話の場」として活用し、
心理的安全性の醸成につなげています。
(自社への展開例)
週1回5分だけ、「良かった点」「次に活かせる点」を伝える
“ミニ・フィードバック”を習慣にする。
Z世代は、短くても具体的なコメントに信頼を感じます。
3.「リバース・メンタリング」で世代の強みを掛け合わせる
上下関係ではなく、“学び合い”がキーワードです。
ある広告代理店では、「AIメンタリング制度」を設け、
若手社員が“AIメンター”として経営層に
AI活用を指導する仕組みを導入。
若手は経営に関わる実感を得て、経営陣は若手視点から学ぶ
という“逆メンタリング”で世代の壁を溶かしています。
(自社への展開例)
自社でも、「Z世代が上司に最新ツールを教える勉強会」
を企画してみてはどうでしょうか?
“教える若手”と“学ぶ上司”の関係は、
4.「柔軟な働き方+成長機会の設計」で価値観ギャップを埋める
Z世代は“自由”と“成長”の両立を求めます。
柔軟な働き方を提供するだけでなく、
その中で「どう成長できるか」を見せることが大切です。
ある広告代理店では、20代社員だけの横断組織を立ち上げ、
自分たちでテーマを設定し、経営に提言しています。
また「若手抜擢制度」でプロジェクトリーダーを任せ、
成長と自由を両立しています。
私がご支援している企業様でも若手だけで新事業を
考えているプロジェクト&コンサルタイムがあります。
(自社への展開例)
フレックスタイム制など柔軟な働き方の制度導入を
検討する時など「その自由でどんな力を伸ばしたい?」
をセットで検討してみましょう。
5.「キャリアの道筋を一緒に描く」
Z世代は「この会社でどんな未来を描けるか」を重視します。
ある会社のキャリア対話制度では、若手と上司が
四半期ごとに「自分の成長テーマ」を
話し合う仕組みを導入しています。
“成果だけでなく、学びと挑戦を評価する”
(自社への展開例)
「どんな力を身につけたい?」
「3年後どんな人になっていたい?」を一緒に描く場を持ちます。
“押しつけ型の育成”から“伴走型の成長支援”
6.「発信の場」を渡して、仲間意識を強める
Z世代はSNS世代。
自分の考えや取り組みを発信できると、やる気が上がります。
ある人材輩出企業では、若手社員が自由に社内外へ情報発信
を行う研究的な場を設け、業務改善の提案も投稿形式で共有。
“意見を言える文化”がエンゲージメントを高めています。
(自社への展開例)
社内SNSや朝会で「若手アイデア発表コーナー」
を設けるなど、発言できる場があるだけで、
若手の「この会社で成長できる」という感覚が高まります。
7.「心理的安全性」をチームのルールにする
Z世代が力を出せない大きな理由の一つに、
「否定されることへの恐怖」があります。
逆に、安心して発言できる環境をつくると、
あるソフトウェア会社では、失敗や提案を
歓迎する文化を浸透させ、「誰でも発言できる会議」を標準化。
社員のエンゲージメントが大幅に向上したと報告されています。
(自社への展開例)
会議の最初に「どんな意見でも歓迎」
と明言するだけでも、空気は変わります。
上司が率先して自分の失敗談を語るのも効果的です。
まとめ:世代の違いは“壁”ではなく“可能性”
Z世代の強みは、デジタル力・学習スピード・柔軟性・発信力。
ベテランの強みは、経験・判断力・人間理解。
この2つが掛け合わさると、組織は一気に進化します。
世代の違いに悩むより、違いを活かすリーダーシップへ。
Z世代が輝く組織は、リーダーも一緒に輝ける組織です。
一工夫して、それぞれのよさが輝くチームを
作っていきましょう♪
******
■イキイキ働きたいカッコイイ大人のベースキャンプ「
https://s-kando.com/service/
※登録無料