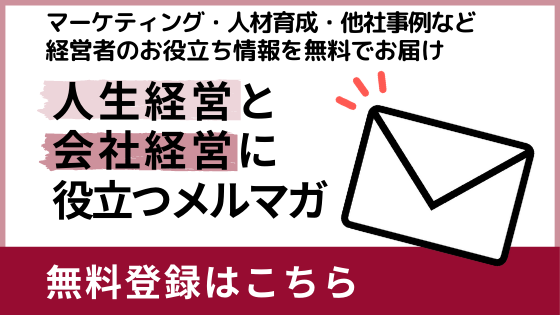眠りが働き方を変える日 ~「ある贈り物」と「あの声」から考える未来の働き方~
チームSKM 吉田です
<家族からの贈り物が教えてくれたこと>
ある日、家族からプレゼントされた「時計」。
手首に装着するスマートデバイス
そう、世間一般には「ウェアラブル端末」と
呼ばれるものです。
心拍数や呼吸数、歩数、心電図・・・、
そして、「睡眠の質」まで記録してくれるという。
正直、最初はピンときませんでした。
健康? 睡眠?
そこまで気にしたことはありませんでした。
もちろん「睡眠が大事」だということは
知っているつもりですが・・・・。
でも、家族は見かねていたのかもしれません。
その贈り物には、
「睡眠こそ一番大事。健康管理をしてね」という
願いが込められていたのだと思います。
<睡眠は、心と体の「再起動ボタン」>
メンタルヘルスマネジメント2種の勉強を通じて、
私はようやく「睡眠の真の意味」にあらためて
気づかされました。
睡眠は、ただの休息ではありません。
それは、心のバランスを整え、身体の修復を促し、
明日を生きるための「再起動ボタン」なのです。
睡眠不足が続くと、交感神経が休まらず、
血圧や血糖は乱れ、心臓や脳に負担がかかり、
免疫力は低下(感染症にかかりやすくなり)、
集中力・判断力・記憶力も落ちていく。
そして、うつ病や不安障害など精神面の
不調にもつながります。
これらが、いわゆる「睡眠負債」。
もはや感覚ではなく、科学が示す事実なのです。
<働き方改革は「睡眠改革」>
厚生労働省が進めてきた「働き方改革」は、
単に残業を減らすことではありません。
その本質は、「人が健康に働き続けられる社会」を
つくることにあります。
・時間外労働の上限規制(罰則付き)
・勤務間インターバル制度(終業から始業までに11時間の休息)
・労働時間の客観的把握(タイムカード・IC記録など)
これらはすべて、睡眠時間の確保=健康維持の基盤と
いう考え方に基づいているものです。
そして、その「11時間の休息」こそ
人が再び創造性を取り戻す時間なのかもしれません。
睡眠は、メンタルヘルスのセルフケアの柱で、
ラインケアの視点でも、部下の睡眠状況に気づくことが
早期支援のきっかけになります。
<聞こえてきた「あの声」>
最近、ある政治家の発言が話題になりました。
「もっと働けるように、労働時間の規制を見直すべきだ」
「ワークライフバランスという言葉を捨てよう」
この発言は、政治的な意気込みとして
受け止めるべきものかもしれません。
ただ、事実として「労働時間の規制緩和」が
議論されていることは確かです。
その背景には、経済成長や生産性向上への期待もあります。
しかし、現場では「長時間労働の容認」と
誤解される可能性もあります。
だからこそ、今こそ「睡眠の価値」を再確認すべきなのです。
<テクノロジーが教えてくれた“眠りの通信簿”>
家族からの贈り物、あのスマートデバイスは、
毎朝、私の「眠りの通信簿(睡眠スコア)」を
そっと見せてくれます。
「深い睡眠:1時間2分」「心拍数:平均58」
「呼吸数:16回/分」 「睡眠時無呼吸」
え、こんなに細かくわかるの?
それはまるで、「ちゃんと休めてる?」と
問いかけられているようなのです。
<中小企業のリーダーの皆さんに伝えたい>
中小企業の現場では、制度よりも“空気”が優先されがちです。
「みんな頑張ってるから」「今が踏ん張りどきだから」
そのお気持ちはよくわかります。
でも、睡眠を削ってまで頑張る働き方は、もう時代遅れです。
最近ではテクノロジーを活用し、
睡眠の質を“見える化”することが可能になりました。
こうしたデータはセルフケアだけでなく、ラインケアにも、
活かせます。
たとえば、1on1で「最近、眠れてる?」と尋ねるだけで、
部下のコンディションを知るきっかけになる。
あるいは、チームで「睡眠スコア」を共有し合うことで、
健康意識を自然に高める文化も生まれるでしょう。
メンタルヘルスマネジメントの視点から見ても、
睡眠は「心の安定」と「職場の安全」を守る鍵になります。
<未来の働き方は、「よく眠ること」から始まる>
「働き方改革」は、もはや“制度”ではなく“文化”です。
そしてその文化の中心に、「睡眠」があります。
「よく眠り」「よく働き」「よく生きる」。
そんな未来を、私たち自身の手でつくっていきましょう。
そして、家族の想いに気づける働き方を、
私たち自身が選び取っていきたいものです。
** 是非ご参加下さい *******
■イキイキ働きたいカッコイイ大人のベースキャンプ「
https://s-kando.com/service/
※登録無料