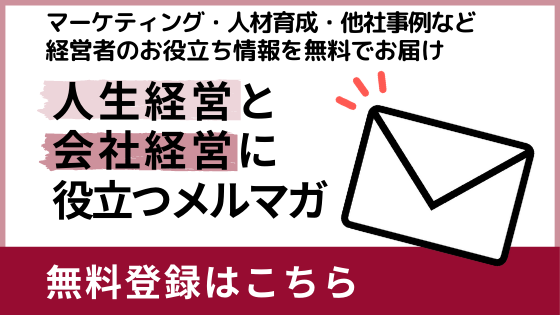もはや上手い解説だけでは価値がない
生成AIの進化が止まりませんね。
GoogleのNotebookLMがリリースした
「音声概要(Audio Overview)」機能が
話題を呼んでいます。
アップロードしたPDFやWeb、YouTube動画などを、
2人のAIホストによる自然な会話形式で要約し、
まるでポッドキャストを聴くように学べます。
日本語を含む50以上の言語に対応!
NotebookLMの音声概要は、AI同士の対話を通じて
対話相手との“共感”や“問いかけ”を演出し、
単なる読み上げでは生まれない親近感まで醸成します。
まるで社内ポッドキャストのような親しみやすさが、
学びを促す効果も期待できそうです。
生成前に「カスタマイズ」ボタンから
特定のトピックに焦点を当てるよう指示したり、
専門性のレベルを調整したりも指示して調整できますし、
「初心者向けに」「関西弁で」などのプロンプトを入力すれば、
自社の文化やトーンに合わせた解説も仕立てられます。
※私が試しに関西弁と指示すると、正直ちょっと
わざとらしかったですが、そこはご愛敬。
今後、どんどん自然になっていくでしょう。
膨大な資料や専門的なドキュメントも
スムーズに理解できますね。
人材育成・教育も変わっていきますね!
ただし、どれだけ高性能でもAIはあくまでアシスタント。
誤情報や音声の乱れを含むこともあります。
最終チェックや文脈の補完は人間の役割です。
そして本当に価値を生むのは、
人と人の信頼関係と社風を土台にして、
生成AIの力も上手に使うことですね。
生成AIの活用力は比較的短期間で高めることができます。
それ以上に、生成AI自体がとてつもないスピード
で進化しつづけていきます。
本当に差別化になるのは、信頼の関係性や
社風になってくると思っています。
これは、丁寧に一つずつ育んでいく必要があります。
時間も手間も掛かりますので、今すぐ取り組んで
いただきたいです。
今すぐ実践できる第一歩は、
部下との対話の場を増やすこと。
たとえば週に一度の短い「コーヒーブレイク」的な
対話の時間をとってみてもいいと思います。
対話を重ねることで心理的安全性が高まり、
組織全体の成長エンジンが回り始めます。
情報整理や解説の巧拙だけでは、成熟した
ビジネス環境で差別化できません。
これからのリーダーに求められるのは、
“どんな関係性”を育んで、その上で、
組織として生成AIも上手く活用していくか?です。
ぜひ今日から、部下と本音で語り合う時間を
意識的につくってみてください。
生成AIが発展すればするほど、表面的な内容での
差異化・差別化は難しくなります。
信頼に裏打ちされたコミュニケーションこそが、
新たな価値を紡ぎ出す源泉になります。
** 是非ご参加下さい *******
■志とリーダーシップ・ビジネスナレッジを磨く
無料・共育コミュニティ「さんよし会」
https://s-kando.com/service/