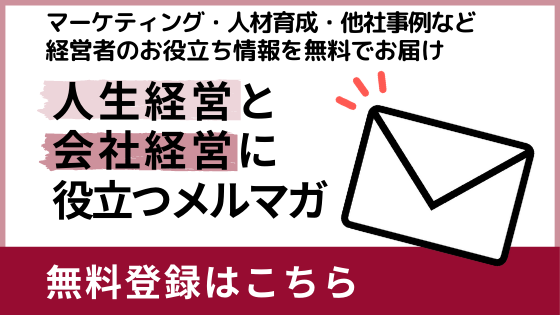環境適応業としてAI時代対応を考える
前号では、NotebookLMの音声要約の話をしました。
それ以外にもChatGPTのエージェントモデルなど
進化は留まることをしりません。
これの是非を言っても意味がありません。
これはGAFAMでも、ほとんどコントロールできない
ですし、国家でも難しいことです。
私たちにとっては全くコントロールできない外部環境です。
喩えるなら、運動会を開催するときに、
天気をコントロールしようとするようなものです。
なので、私たちが考えることは一つ。
AI時代にどう対応していくか?だけです。
見て見ぬ振りして、衰退するか?
積極的に向き合っていくか?
だけです。
特にAI時代を考えた時に、
今のAIだけを見ていたらダメです。
AIのように人は、組織は、クイックには変われないからです。
未来は分からないけれど、
ある程度見通しをもって、人づくり・組織づくりを
していく必要があります。
さて、将来を見据えた時に、
どんな対策が必要でしょうか?
こんな記事を見つけました。
国際労働機関(ILO)が2025年5月、生成AIが
雇用に与える影響について分析した最新研究レポート
「Research Brief AI and jobs: A 2025 update」です
~世界の雇用の4分の1が生成AIに代替される可能性~
https://www.jil.go.jp/foreign/
さあ、ここから何を考えますか?
高校生でも分かるレベルで推論モデル(ChatGPT o3)
で、上記記事をベースに考えてもらいました。
以下は、そのアウトプットをさらに私が少し整理
しなおしたものです。
正しいかどうか?当たるかどうか?ではなく、
このようなことを考えて欲しいのです。
■今なぜ考える必要があるのか?(背景)
・AIは24%の仕事に影響
事務的な仕事(書類作成やデータ入力など)
・完全に自動化は難しい
AIの技術は進んでいるが、まだ全部を自動でこなすのは難しい。
人がチェックしたり、修正したりする部分が必要。
・マルチメディアやデータ設計もAIが伸びている
画像や音声を扱う仕事、データベースの設計など、
今まで人が専門的にやっていた分野もAIが手伝うようになってき
■どう解釈(読み取る)すればいい?
・AIの得意分野は「決まった手順」の仕事
手順がはっきりしている仕事(例:会議の議事録作成など)
↓
逆に人が得意なのは「あいまいな場面」や「責任が重い仕事」
トラブル対応やみんなの意見を調整する、
↓
単にAIの使い方を覚えるだけじゃダメ
↓
「AIにどう働いてもらうか」を設計して、
↓
更に影響を受けやすい人・職種がある事実がある
↓
事務作業が多い職種や、国によって影響度が違う。
社内でも公平に学び直し(リスキリング)が大切。
■中小企業(または少人数のチーム)でもできる5つのアプローチ
(1)AIの仕事設計と品質チェックがカギ
自分のルーチンを分解して、
(2)トラブル対応や話し合いが差をつくる
よくあるトラブル例をまとめ、どう判断するか型を作る。
(3)マルチメディア時代の上流工程(要件定義)が武器
使うデータとその権利、安全対策をチェックリスト化する。
(4)仕事の役割をスキルで再設計する
誰が得意な部分かを明確にし、
(5)現場リーダーが小さく回して突破する
90日で「チーム内で1つの作業を自動化+チェック」して、成果
AIの時代は、「AIをただ使える人」ではなく、
「AIと人がうまく組み合わさ、しくみを作る人」が
大きな価値提供ができます。
ツールを覚えるだけでなく、仕事そのものをデザインし直す。
それがリーダーのこれからの必須スキルですね。
** 是非ご参加下さい *******
■志とリーダーシップ・ビジネスナレッジを磨く
無料・共育コミュニティ「さんよし会」
https://s-kando.com/service/