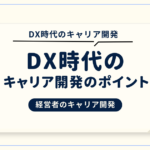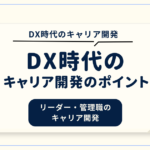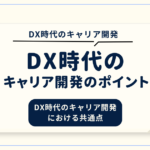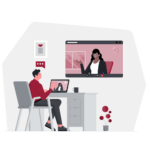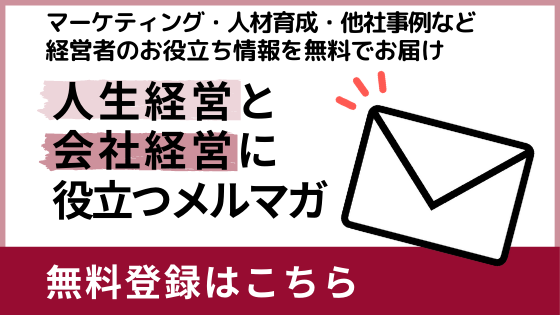ベイズの定理で“勘と経験”をアップデートする
先日MBAにて「ベイズの定理」について学びました。
ベイズの定理自体は18世紀のベイズ牧師
(数学者であり、哲学者でもあった)頃からのもので、
昔からある定理なのですが、
これは第四次産業革命時代・データ・テクノロジー時代に
極めて重要な考え方でもあると感じました。
仕事の進め方、経営についてもそうですし、
VUCA時代におけるキャリア論にもつながると思います。
そういうわけで、私の回の3回に渡って、
ベイズ定理の詳細ではなく、仕事への活かし方、
経営での考え方、キャリアへの活かし方という観点で
一緒に考えたいと思います。
不確かの中、どう判断するか?
私たちは日々、確信を持てないままに
意思決定を繰り返しています。
営業での提案、プロジェクトの進め方、
あるいは部下の成長支援──
どれも未来がどうなるか分からない中で判断を迫られます。
そんなとき、拠り所になるのが「勘と経験」。
けれどもVUCAの時代、過去の経験だけでは
判断を誤るリスクも増えています。
実際、AI将棋などでもそうですが、人間の思考より
パターンを見いだすAIやデータアナリティクスの
方が、人間はなぜか分からないけれど、
精度の高いアウトプットを出す時代になっています。
そんなデータ・AI時代に改めて着目されているのが
「新しい情報を得たときに確率を賢く更新していく」
ベイズの定理の考え方です。
今の時代、特に重要な考え方の一つになっていますが、
テクノロジー抜きでも応用出来る考え方でもあります。
ベイズの定理とは?
わかりやすく言うと、
「何かの原因があって結果が出たとき、
その結果をもとに原因がどれくらいの確率で
起きているかを計算する方法」です。
たとえば医療診断の場面。
ある病気の確率は低くても、検査で陽性が出れば
「実際に病気である確率」を更新します。
あるいは迷惑メール判定。
怪しいURLがあるメールは
「迷惑メールの確率」を高める材料になります。
つまりベイズの定理は、私たちが無意識にやっている
「仮説と情報のアップデート」を
数理的に整理したフレームワークなのです。
リーダーの意思決定にどう役立つか?
仕事の現場では、この考え方が極めて実践的です。
例えば、営業活動
最初の提案が受け入れられるかどうかは
仮説にすぎません。顧客の反応という
新しい情報を得るたびに確率を更新し、
方針を調整すれば成功率は高まります。
たとえば、リスク管理
兆候やデータが出たとき、それを加味して
「本当に問題が起きている確率」
を更新すれば、過剰反応や見落としを減らせます。
たとえば、部下育成
メンバーの行動や成果を観察するたびに
「この人はどんな強みを伸ばしていけるか?」
という仮説を修正できます。
経験則に新しい情報を積み重ねることで、
より確度の高い支援が可能になるといった具合です。
勘と経験を「アップデート」する
私たちはこれまで、勘と経験を頼りに
意思決定をしてきました。
そこにベイズの定理の考え方を重ねると、
勘と経験が“固定化したもの”から、
“常に更新される資産”へと変わります。
大切なのは、「新しい情報が入ったら
柔軟に確率を更新する」という姿勢です。
そうすることで、不確実な状況でも
現実に即した判断ができるようになります。
さんよし会では、
「人と組織の成長を支える思考法」
についても対話を重ねています。
ベイズの定理のように、一見専門的に見える知恵も、
リーダーとしての在り方に直結します。
私たちが直面する不確実な現実に対して、
仲間と一緒に
「どう仮説を立て、どう更新していくか」
を考える場としても、さんよし会は活かせます。
今回はイントロダクションでした。
次回はさらに、経営に踏み込んで
「確率の更新」について掘り下げたいと思います。