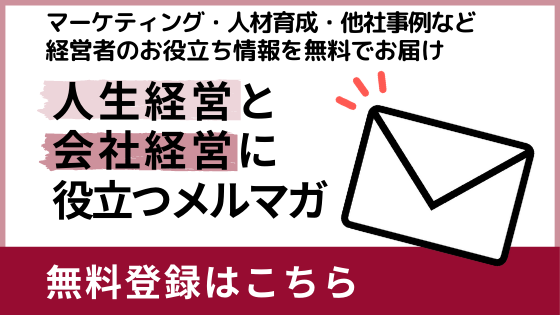組織を活かす「2・6・2の法則」の真実
チームSKM 吉田です。
先日、組織開発関係の勉強会の
ワークショップに参加し、改めて
「組織のあり方」について深く考える
機会がありました。
そこで議論のキーワードのひとつとして
あげられたのが、古くから知られる
「2・6・2の法則(働きアリの法則)」です。
私自身、この法則を初めて耳にしたのは
今から30年ほど前のことです。
当時、自社の人事制度を立ち上げる際、
上司から次のように教わりました。
・2割は言われなくてもやる人
・6割は言えばやる人
・2割は言ってもやらない人
「これは東大生の集団でも同じだ」
「組織の構造や人の分布を前提に、
人事制度を組み立てるべきだ」
その言葉を、今でも鮮明に覚えています。
<「2・6・2」は比率ではなく“自然の摂理”>
その後の実務経験や業務を通じて、
私はこの法則が単なる比率ではなく、
組織が動く際に自然に現れる
「行動パターンの分布」であることを
痛感してきました。
例えば、取引先に調査書類を依頼すると、
・2割は即座に提出
・6割はフォローすれば期限通りに提出
・2割は催促してもなかなか出てこない
という構造が、驚くほど安定して現れます。
これは対応力=能力差というより、
集団における反応パターンの差が生む現象です。
この傾向は、社内で通知や依頼を
発信した場合にも同じように表れます。
<「人を活かす」という思想と2・6・2の接点>
私が長年勤めた会社では、
自然と「人を活かす」組織づくりが根づいていました。
その背景には、松下幸之助氏が語っていた、
・人にはそれぞれ役割がある
・すべての人を同じように動かそうと
するのは誤りである
という“人間観”がありました。
松下幸之助氏が2・6・2の法則を直接
語ったわけではなかったと思いますが、
「人をつくるのが経営」
「人を活かすのが経営」という哲学は、
まさにこの法則の本質と重なります。
つまり、下位2割を切り捨てるのではなく、
多様性を前提に、個々の持ち味をどう活かすか
という視点が重要なのです。
<なぜ「手抜き」が起きるのか?>
勉強会では、この法則を裏付ける理論
としてリンゲルマン効果が紹介されました。
これは、人数が増えるほど一人あたりの
貢献度が低下する「社会的手抜き」の現象です。
・責任の分散
・自分の貢献が見えにくい
・他者に依存しやすい
こうした要因によって、
組織にはどうしても「下位2割」が生まれます。
ここで重要なのは、
問題は個人ではなく、構造にある
という視点です。
働かない2割を排除しても、
残ったメンバーの中から再び2割が生まれる。
つまり、個人を責めても組織は変わらないのです。
<経営者が実践すべき「2・6・2」の活用戦略>
では、この避けられない構造を
どう活かすべきでしょうか。
ポイントは、各層に応じたアプローチを取り、
組織を固定化せず「流動性」を生み出すことです。
1. 上位2割:燃え尽きを防ぎ、知恵を仕組みに変える
自律的に動く層には過度な負荷をかけず、
・彼らの知恵や工夫を言語化し
・標準化・マニュアル化して
・組織全体に展開することにより、
経営者は組織力の底上げを図ることができます。
2. 中間6割:フォローと仕組みで底上げする
この層は「フォローがあれば動く」ため、
期限管理の見える化、役割の明確化、
小さな成功体験によって
上位層へ押し上げることができます。
このような背中を押す仕組みが大事です。
この層が主体的に動き出すことで、
組織の生産性は一気に上がります。
3. 下位2割:構造で改善し、行動のハードルを下げる
個人の資質を責めるのではなく、
(責めても改善しません)
タスクの細分化、配置転換、支援の
仕組みづくりでカバーします。
構造を変えることで行動は変わってきます。
<おわりに:役割が循環する組織へ>
強い組織とは、2・6・2の比率を
固定化させるのではなく、
役割が循環し続ける組織です。
上位層が固定化せず、
中間層が上へと押し上がり、
下位層も改善していく。
最後、事務局の方も
ダニエル・キムの
「成功の循環モデル」を引き合いに
出されていました。
こうした「動きのある組織」こそ、
変化に対応できる力を備えています。
「2・6・2」は、消すべき問題ではなく、
組織をより良く動かすための指針です。
さて、あなたの組織ではどうでしょう。
今、2・6・2のどこに「滞り」が
生まれているでしょうか。
さんよし会では、
この「構造の滞り」を言語化し、
役割が循環する組織へと設計し
直す対話を行っています。
是非、ご参加ください
*********
■イキイキ働きたいカッコイイ大人のベースキャンプ「
https://s-kando.com/service/