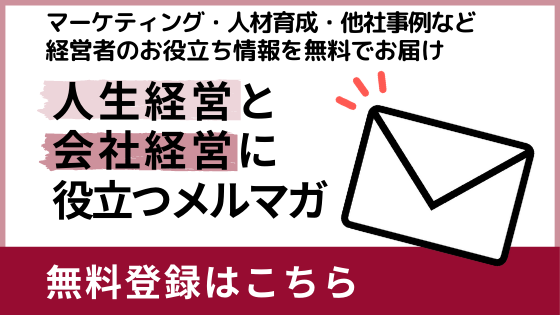人を育てる「良い質問」とは?
チームSKMの池原です。
私は日ごろから質問力を鍛えることを意識しています。
質問力は、
今回は特にビジネスの現場で経営者やリーダーが意識すべき
質問のコツをいくつかお伝えできたらと思います。
なぜ今、質問力が重要なのか。
現代のビジネス環境は「VUCA時代」と呼ばれています。
VUCAとは簡単に言うと「変化が目まぐるしく、
ということです。
このような変化の多い時代に対応するためには
“自発的に考え、動ける人材”が必要です。
このような人材を育てるためには、“教える”のではなく
“自分で考えさせる”、
「質問は相手を動かす魔法」
これはデール・カーネギーの著書「人を動かす」
“人間は他人に言われたことには従いたくないが、
ことには喜んで従う。つまり命令するのではなく、質問をして
相手に思いつかせればいい”
この本は1936年に書かれたものですが
この真理は今も変わっていません。
社員が前向きに自ら考えて働く会社を作るために
質問の力を活用しましょう。
では本題です。
まず質問力の持つ力について簡単にご説明すると
質問には大きく5つの目的があります。
1.情報を得るため
これは現状把握のためのものです。一番頻繁に使います。
2.相手を喜ばせるため
相手の努力や成果を認め、褒める質問です。
3.相手に考えさせる
具体的には「この課題を解決するために、他にどんな方法が
考えられる?」
4.相手に行動を促す
どうすれば目標達成が出来るか、相手の頭の中から具体的な行動を
引き出す質問です。
5.盲点に気付かせる
今までに考えもしなかった視点を相手に与えることで新たな気づき
促します。
ビジネスの場ではこれらの5つの質問を駆使して
相手に考えさせて行動を促すことが求められます。
では、実際の例を紹介します。
例1.納期が守れない部下に対して
悪い例:「どうして期日を守れないの?」
これは相手を非難する質問であり、何も生み出さず
反発を招きます。
良い例:「今回期日を守るために、どのような工夫をしたの?」
これは相手の苦労を認めつつ、改善策を探る質問です。
例2.主体性のない部下に対して
悪い例:「もっと自分で考えることはできないの?」
高圧的な言い方は部下の主体性だけでなく、
モチベーションも下げてしまいます。
良い例:「この件について、○○さんどんなアイデアを持ってる?
おそらく普段主体性のない部下は、何のアイデアもないでしょう。
それでも構わないと考えます。一旦、
大事だと思います。
例3.新たな企画に尻込みする部下に対して
悪い例:「これ失敗したらどうするの?」
不安を煽る言い方は、部下をさらに尻込みさせてしまいます。
良い例:「この企画に対して、どんな不安を感じてる?」
相手の気持ちに寄り添い、「こちらから何かできることはないか」
と聞く。こういう寄り添いがあると「じゃあ頑張ってみよう」と
いう気持ちになります。
ここまでをまとめると悪い例はすべて「ネガティブクエスチョン」
悪い方向の質問です。部下に仕事をお願いするのであれば
その仕事を通じて部下の成長を促し、自発的に考え、動ける人間に
なってほしいですよね。
今現在、何も意識していない会社様は、質問の大切さを
意識し、
部下の成長は、上司である皆様の成長にもつながります。
そして上司が成長することで会社が成長すると考えます。
社員が前向きに自ら考えて働く会社、
幸いです。