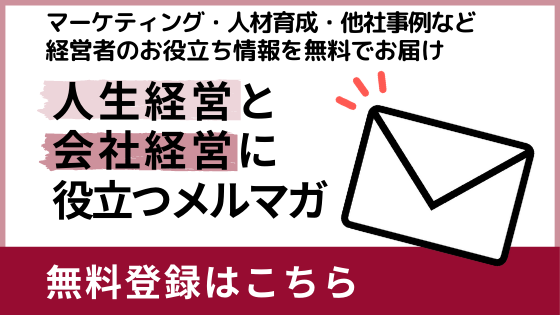コンプライアンス違反の背景と5つの視点
チームSKM 経営コンサルタントの吉田です。
昨日の佐々木さんのブログで
「3カ月に1回プロフィールを
書き換えてみよう」という提案がありました」
私自身 友人たちと共有しているプロフィールがあり、
気づけば、1年前のものになっていました。
「見直しをしよう」と さっそく連絡を取り合いました。
自分の為に 友人からの刺激をもらいながら、3カ月
ごとのプロフィールの更新を目指したいと思います。
さて、最近のニュースで、
「選挙の不正(水増し票)」、「下請法違反」、
「学校内暴力」、「SNSでの誹謗中傷」など、
企業・組織の不祥事が後を絶ちません。
どの会社も組織もコンプライアンス教育を実施
しているはずなのに、なぜ違反は繰り返される
のでしょうか。
私自身、企業内で長年コンプライアンス研修を
担当してきましたが、知識だけの「当たり前教育」
では限界があると感じていました。
結局、誰も法律違反はしないものと思っているからです。
一方通行の講義形式のコンプライアンス研修では
対岸の火事のように受け止められ、形骸化という問題に
直面しています。
毎年10月は
「コンプライアンス月間(企業倫理)」として
多くの企業が研修を実施していますが、
皆さんの会社ではどのような取り組みを
されていますか?
日本経団連の統計によると
コンプライアンス研修について
大手企業の約9割がこの月間に研修を実施しています。
一方で、「約7割の企業では毎年ほぼ同じ内容で形骸か
している」という課題も認識されています。
帝国データバンクの「コンプライアンス違反企業の
倒産動向調査(2024年度)」によると、
違反による倒産は過去最多の379件に達し、
倒産全体の約3.8%を占めました。
特に
「粉飾決算」「不正受給」「資金使途不正」が
急増しており、社会の目はますます厳しく
なっています。
しかし、
このように、件数や割合を伝えるだけでは、危機感は
社員には浸透しません。(心に刺さりません)
そこで、私はケーススタディやグループワークを
用いた研修を提案し、実施してきました。
理論と実践(演習)を交えた講習が必要です
とは言え、実際のその原因となる
理論を学ぶのも大事です。
このブログでは理論の一部をご紹介します。
【違反企業に共通するのは職場風土の歪み】
「なめた」──これくらい大丈夫、バレないだろう
「隠した」──怒られるから黙っておこう
「嘘をついた」──確認したと言い張る
「言えない空気」──おかしいと思っても声を上げられない
こうした“会社の常識”が“社会の非常識”となり、
信用失墜・組織崩壊へとつながるのです。
【コンプライアンス順守の5つの視点】
1.法令順守:その行為は法律に違反していないか
2.経営理念:会社の方針に反していないか
3.社会常識:社会に通用するか
4.消費者視点:顧客はどう感じるか
5.自分の心:自分自身が納得できるか
法令の知識ベースだけでなく、経営理念や考え方(あり方)の
レベルで 判断することが、真のコンプライアンスです。
特に5番目の自分の心に胸をあてて考えるというところは
直近お邪魔した企業でも実践されていました。
(下記の内容をビジョン・
行動指針の一部に掲げられていました)
判断基準として
「人間として正しいことを追求する」
なんか 格好いいですね
【企業ができる対策】
・階層別・定期的な教育の継続(マンネリの打破)
・「風通しの良い職場風土」をつくる
心理的安全性の確保
・経営理念などの「5つの視点」を
浸透させ・体現すること。
※毎年10月は
「コンプライアンス違反防止(企業倫理)月間」
として経団連も啓発を強化しています。
形式的な講習だけでは、対岸の火事のまま。
eラーニングだけで済ませていませんか?
倫理観の低下、内部通報体制の不備、
研修の形骸化 今から準備して
10月の強調月間に備えてください。
【継続は力なり】
コンプライアンス順守には
「熱心さ」と「工夫」が大切です。
** 是非ご参加下さい *******
■志とリーダーシップ・ビジネスナレッジを磨く
無料・共育コミュニティ「さんよし会」
https://s-kando.com/service/