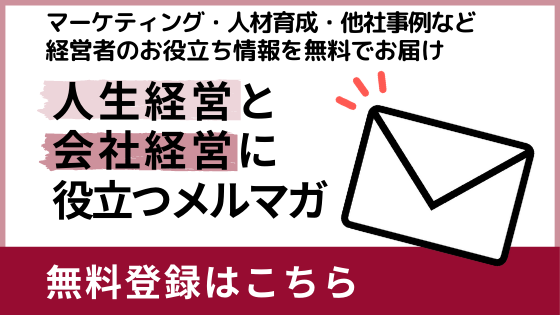甲子園のドラマから考える戦略の正しさ
チームSKM 経営コンサルタントの池原です。
今年も甲子園のシーズンがやってきました。
私も甲子園球場の近くに住んでいることもあり、
甲子園と言えば様々なストーリーが生まれますが
今日は私が好きなストーリーをお伝えしたいと思います。
みなさんは1992年、星稜高校VS明徳義塾の試合で
松井秀喜が5連続敬遠された話はご存じでしょうか?
この試合は、当時物議をかもし、明徳義塾の勝ちに
対するこだわりがスポーツマンシップに反すると、
当時の明徳義塾の馬淵監督はバッシングされたものです。
しかし、あまり注目されていませんが、
その5打席敬遠の次の5番打者、月岩選手。
この5番打者は実は非常に優れたバッター
だったのですが、その試合ではすべて凡退したのでした。
(うち1回はスクイズに成功)
今回は、この試合の裏にあるドラマに触れながら
ビジネスにおきかえて考えてみたいと思います。
この試合、明徳義塾の馬淵史郎監督は、
星稜の4番打者、松井秀喜選手に対し、
全5打席で意図的な敬遠を選択するという、
前代未聞の戦略を実行しました 。
この戦略の最大の動機は、高知県代表として
一つでも多く甲子園で勝ち進むことでした 。
実際に結果として、明徳義塾は3対2の僅差で勝利を収めました 。
彼は松井選手を「高校生の中に一人プロが
混じっているかのような選手」と評価し、
彼との勝負を避けることが勝利への最短ルートだと見極めました 。
それにあたり、次のバッターである5番打者の月岩選手。
馬淵監督は松井を敬遠する戦略をとるために、
5番打者を徹底的に研究したそうです。
実際にこの試合で月岩選手はほとんどチャンスで打席が回ってきま
相当なプレッシャーだったと思います。
そのプレッシャーと弱点を研究され
彼は結果を残せませんでした。
残せないどころか試合が終わった後の彼の人生は、
後ろ指を指される人生となりました。
周囲の期待に応えられず、批判や劣等感を受け、
実際に決まっていた大学は、
暴力事件をきっかけに取り消しになったり、
野球人としての人生だけでなく、
幸せな人生が奪われてしまったといいます。
そんな後ろ向きな生き方をしていたある日
プロ野球からニューヨークヤンキースに移籍し
華々しい活躍をしていた松井秀喜。
テレビではチャンスの場面で、前の打者が
敬遠された松井選手の姿があったそうです。
月岩選手は「敬遠されてチャンスに回ってきた
気持ちを味わえ」と思ったそうです。
結果はどうなったか?
松井は見事ホームランを打ちます。
逆境をいとも簡単にはねのけた彼の姿を見て、
月岩選手もいつまでも過去に縛られている自分の姿を恥じ、
前向きな気持ちを取り戻したという話です。
話を戻します。
この明徳義塾の馬淵監督がとった作戦。
馬淵監督の判断は「1勝(短期目標)を達成する」
という明確なゴール設定において、
極めて合理的で「正しい」判断だったと言えます。
ただこの極端な戦略は、当時激しいバッシングを生みました。
ではビジネスの場合に当てはめると、
「短期的な利益を追求する」という経営戦略のように思います。
そこには倫理も、商売上の正しさもない非情な選択です。
ビジネスは短期勝負ではありません。
つまりこの馬淵監督の作戦は「商売(長期的な持続性)」
という観点からは、大きな「間違い」
企業が一時的に大きな利益を上げたとしても、
その方法が社会的な規範や顧客の期待に反するものであれば、
ブランドイメージは著しく毀損され、
長期的な信頼を失うことになります。
高校野球における「教育の一環」「正々堂々とした勝負」
という暗黙のルールは、ビジネスにおける
「企業の社会的責任(CSR)」「公正な競争」
「顧客との信頼関係構築」といった概念に置き換えられます。
短期的な利益追求のためにこれらを無視すれば、
たとえ法的に問題がなくても、社会からの信用を失い、
顧客離れ、優秀な人材の流出、取引先からの敬遠など、
長期的な事業継続を困難にする要因となりかねません。
またこの戦略では、当時敬遠を実行したバッテリー側にも
心に後ろめたさやバッシングなどの影響も残しました。
これもビジネス上の短期目標を追求して、
過度な負担を強いられ、疲弊する社員の姿に重なります。
チームの士気ややりがいにも悪影響を及ぼします。
そういう意味でもビジネスにおいてはこのような決断をするべきで
実際に、このあと明徳義塾は次の3回戦で広島の広島工に0-
この事例をビジネスに当てはめると、
・短期的な目標達成は重要だが、それだけでは不十分:
一過性の勝利や利益は、企業の存続を保証しません。
短期目標を達成しつつも、長期的な視点に立った戦略が必要です。
・「商売のルール」は信頼の基盤:
企業は、単に利益を追求するだけでなく、
業界の慣習、社会倫理、そして顧客や社会との約束といった
「商売のルール」を遵守することで、
信頼という無形資産を築き、持続的な成長の基盤を確立します。
・倫理的な経営は長期的なブランド価値を形成する:
批判を浴びるような手段で得た利益は、
公正で倫理的な経営は、企業のブランド価値を高め、
顧客ロイヤルティ、優秀な人材の獲得、
そして社会からの支持を得る上で不可欠です。
明徳義塾の事例は、1勝(短期目標)を達成する上では
「正しかった」かもしれませんが、「商売(長期的な持続性)」
という観点からは疑問符がつく経営判断であったと言えるでしょう
とはいえ、当時私は、この試合を見て興奮したのを覚えています。
また色々なことを考えさせられる試合になりました。
さて今年の甲子園ではどのようなドラマが生まれるでしょうか?
皆さんもその熱いドラマに注目しましょう。
** 是非ご参加下さい *******
■志とリーダーシップ・ビジネスナレッジを磨く
無料・共育コミュニティ「さんよし会」
https://s-kando.com/service/